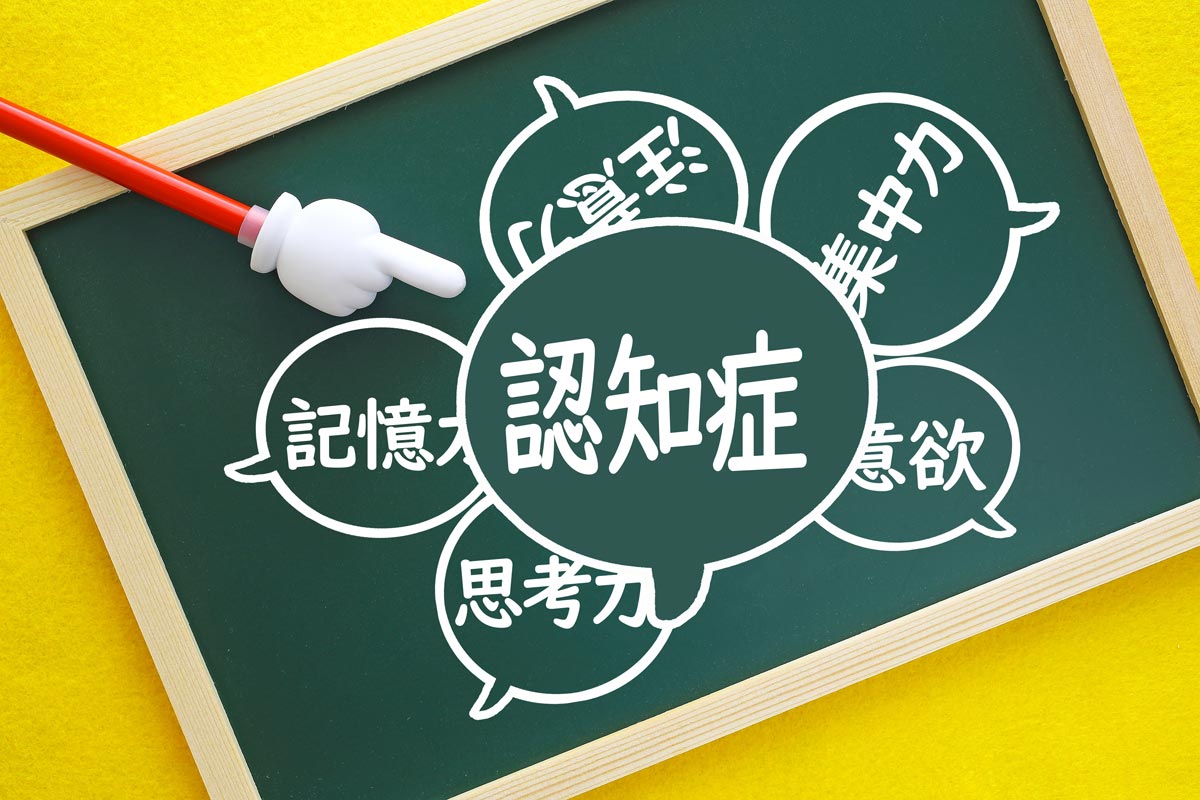更新日:
ボケ防止に役立つ7つの生活習慣!年代別のポイントも紹介
認知症を完治する薬は存在しないため、認知症にならないこと、つまりボケ防止が大切です。
2025年には65歳以上の5人に1人が認知症患者になると予想されています。
この記事を読むことで、ボケ防止に有効な7つの生活習慣がわかります。
高齢者の方はもちろん、ご家族の方にも抑えるべきポイントが把握できますので最後までお読みください。
ボケ・認知症のリスク
認知症を発症すると次のようなリスクが生じます。
- 認知機能の低下
- 介護者や家族の負担増大
- 治療費や介護サービス費用増大
- 社会的孤立
- 感染症のリスク増大
本人や家族の精神的負担だけでなく、経済的負担も増大します。
認知症は、健康面や日常生活全般にさまざまな影響を及ぼすため、予防が非常に重要です。
認知機能が低下すると活動量の減少につながり、足腰が弱ることで転倒やケガのリスクも高まります。
また、外出を控え人との交流が減少することで、社会的孤立を引き起こします。
運動の機会や他者との関わりが減少すると、さらに認知機能の低下が悪化し悪循環が起こるのです。
厚生労働省の発表によれば、2025年には65歳以上の認知症患者が約700万人に達し、高齢者の約5人に1人が認知症を発症すると予測されています。
さらに、65歳未満で発症する若年性認知症や認知症予備軍とされる軽度認知障害(MCI)のリスクも見逃せません。
こうした状況を踏まえると、日々の生活で積極的に予防に取り組むことが大切です。
そこで次章では、ボケ防止のポイントについて解説します。
参照:厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
以下の記事では、認知症の初期症状や対応方法を解説しています。あわせてご覧ください。
年代別!ボケ防止のポイント
ボケ防止は若いうちから始めることが推奨されています。
ボケ防止のポイントは健康な生活習慣を身に付けることです。
三大要素と呼ばれる、食事・睡眠・運動が健康ののバランスをとって生活すると良いでしょう。
食事・睡眠・運動のバランスが大事なことは、認知症予防の10か条でも紹介されています。
- 塩分と動物性脂肪を控えたバランスのよい食事を
- 適度に運動を行い足腰を丈夫に
- 深酒とタバコはやめて規則正しい生活を
- 生活習慣病(高血圧、肥満など)の予防・早期発見・治療を
- 転倒に気をつけよう 頭の打撲は認知症招く
- 興味と好奇心をもつように
- 考えをまとめて表現する習慣を
- こまやかな気配りをしたよい付き合いを
- いつも若々しくおしゃれ心を忘れずに
- くよくよしないで明るい気分で生活を
年齢別にボケ防止のポイントを見ていきましょう。
20代から30代
青年期に良い習慣を身に付けておけば、将来認知症を発症するリスクをぐっと下げることができます。
歳をとってから身に付けにくい運動習慣を付けるのがおすすめです。
一方で偏った食事や過度な飲酒、喫煙は、認知症の原因となる動脈硬化を促進するため、習慣付けないように注意しましょう。
40代から50代
中年期では高血圧や肥満が認知症のリスクを高めます。
食事の際は、塩分やカロリーの摂り過ぎに注意しましょう。
BMI(体格指数)30以上で肥満とされているため、健康診断を受けたら値を確認するようにしてください。
運動習慣を付けるのが難しい方は、エレベーターを使わずに階段を使うなどできることから始めましょう。
65歳未満で発症する認知症は「若年性認知症」といい、約3割は50歳未満で発症すると発表されています。
平均発症年齢は51.3歳で女性よりも男性に多いのが特徴です。
高齢者に比べ、身体機能が高く動作も早いため、対応が困難と感じる方も多くおられます。
また、認知症により仕事ができなくなったことで、生活が困窮する方も珍しくありません。
詳しくは以下の記事で紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:若年性認知症とは?なりやすい人の特徴や高齢者との違い・症状や予防方法を解説!
60代以上
更年期では、喫煙や糖尿病、うつといった認知症発症の要因があります。
なかでも喫煙は認知症の発症リスクが高いといわれているため、できるだけ早く禁煙することをおすすめします。
仕事を定年する方も増え、家に閉じこもりがちになる方もいます。
できるだけ外気に触れたり、他者と関わったりすることで良い刺激となりボケ防止につながります。毎日外を散歩するだけでも十分です。
運動によるボケ防止
1つ目の予防法は運動です。
運動することで筋力の低下を防ぐほか、メタボの予防にもなります。
運動は中強度と高強度の有酸素運動を組み合わせるのがよいでしょう。
中強度の運動
- ウォーキング
- 庭仕事
- 水中のエアロビ
- 自転車漕ぎ など
高強度の運動
- ランニング
- 水泳
- サイクリング
- ハイキング
- 縄跳び など
高齢者は加齢に伴って活動量が低下し、行動範囲も狭くなりがちです。
自分の体力と相談しながら、苦にならずに続けられるものを選びましょう。
以下の記事では、認知症かも?と感じる方向けにセルフチェックの方法を紹介しています。参考にしてみてください。
食事によるボケ防止
2つめの認知症の予防法は食事です。
栄養バランスの悪い食生活を続けていると、健康状態が悪化してしまいます。
食事で認知症を予防するには、以下の食べ物をバランスよく摂ると効果的です。
- 全粒穀物
- 青魚
- オリーブオイル
- ナッツ
- 野菜や果物 など
さらに自分で料理するのもボケ防止の観点では効果があります。
認知症の中核症状には実行機能障害と呼ばれる症状が含まれ、計画を立てたり工程を進めたりするのが難しくなります。
自分で料理を作るには、必要な食材の準備や段取りを考えるなどして、頭を使います。
そのため、料理をするのは頭の回転と手足の運動機能の両方を必要とし、ボケ防止として効果が高いといえるでしょう。
避けた方がいい食事
毎日料理するのが大変だと感じる方も多いでしょう。
しかし、以下のような食べ物は避けることをおすすめします。
- 加工肉
- 菓子パン
- ラード、マーガリン
これらの食品には、添加物やトランス脂肪酸が多く含まれるためです。
食事は毎日のことなので、思い当たる方は速やかに食生活を見直しましょう。
また、塩分の摂り過ぎは高血圧や動脈硬化のリスクを高める原因になるため、1日6.5~7.5mgまでに抑えるとよいとされています。
よく噛んで食べることも重要
食事内容以外にも、よく噛んで食べることが推奨されています。
歯で噛んだ際、歯根膜と呼ばれる器官が沈んで血管を圧縮することにより、血液を脳に送ります。
つまり噛めば噛むほど血液が脳に送られるため、脳が活性化して認知症になりにくくなるという訳です。
実際、歯が少ない人は20本以上歯がある人と比べて認知症になるリスクが高いという調査結果もあります。
たとえ歯が少なくても、義歯を使用することで認知症を発症するリスクを抑えられることも分かっています。
このことからよく噛むことがボケ防止につながることは明らかです。
社会活動によるボケ防止
3つめのボケ防止は、社会活動です。
定年退職して社会との関わりが失われると、社会的孤立が進みます。社会的孤立は認知症の原因のひとつです。
WHOの報告によると、孤独は1日15本の喫煙に相当する健康被害を与えるといわれています。
孤独は認知症だけでなく、うつの原因ともいわれており、軽視できません。
孤独感を解消する方法のひとつに、趣味を通じたコミュニティへの参加があります。
新しい人との関わりを持ち、刺激を受けることによって認知症の予防につながるでしょう。
日常生活で取り入れられるボケ防止
日常生活で取り入れられるボケ防止を紹介します。
- テレビゲーム
- 脳トレ
- コグニサイズ
- デュアルタスク
家庭内はもちろん、デイサービスでも取り入れられているものもあります。
テレビゲーム
最近では、オンライン上で競技や対戦を行うeスポーツがボケ防止に効果があると注目を集めています。
eスポーツは、ゲームを楽しみながら情報処理能力の向上やマルチタスク能力の向上、脳の活性化など、ボケ防止の効果が期待できます。
自宅に居ながらオンラインでコミュニティに参加でき、社会との関わりを持てる点もeスポーツならではのメリットといえるでしょう。
脳トレ
間違い探しやことわざクイズ、パズルなど、頭を使うことで脳に刺激が加わり、活性化に繋がります。
脳の領域で感情や学習、記憶を司るのが前頭葉です。
脳トレは前頭葉に働きかけることで、脳の老化スピードを落とします。
継続が大事なため、問題のレベルを簡単すぎず、難しすぎないものを選ぶことが大切です。
脳トレの素材はインターネット上で無料ダウンロードできるものもあるので、上手く活用するとよいしょう。
コグニサイズ
コグニサイズとは、コグニションとエクササイズを合わせた造語です。
もともと国立長寿医療センターが開発した運動と計算やしりとりなどを組み合わせ、認知症の予防を目的とする取り組みがきっかけです。
たとえば、イスに座って足踏みをしながら数を数えて、3の倍数の時だけ手を叩く運動がコグニサイズに当たります。
デュアルタスク
デュアルタスクとは、2つのことを並行して行うことを指します。
例えば運動しながら計算したり、歌いながら洗濯物を畳んだりということがデュアルタスクに当たります。
脳を働かせて血流を良くしながら、体を動かすことが認知症予防に効果があるという調査報告もあるため、上手く活用してみてください。
まとめ
ボケ防止には、若いときからの生活習慣が大きな影響を与えることがあります。
認知症は高齢者だけのものではありません。
自身の生活習慣を見直し、適度な運動やバランスの良い食事、社会活動への参加を取り入れてボケ防止を始めていきましょう。
認知症や物忘れでお困りの方に向けて、さまざまな福祉用具を展開しています。
お困りの際は、ぜひヤマシタまでご相談ください。
以下の記事もぜひ参考にしてみてください。