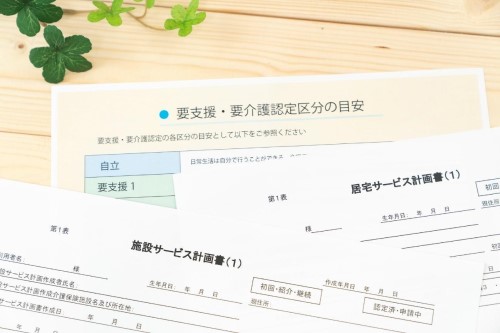更新日:
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)とは?判定基準や評価のポイントを解説
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)は、どのように決まっていくのでしょうか。
本記事では、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の判定基準や評価ポイント、介護現場でどのように活用されているか解説します。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)とは
日常生活自立度(寝たきり度)とは、厚生労働省によって定められた、障害高齢者がどれくらい自立した生活を送れているかを判定する評価尺度です。
主に要介護の認定調査や、介護サービスに関する書類などに使用されています。
日常生活自立度には、以下の2つの種類があります。
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
- 認知症高齢者の日常生活自立度
まずは「寝たきり度」と言われる、障害高齢者の日常生活自立の判定基準について解説します。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の判定基準
障害高齢者の日常生活自立度の判定基準は以下のとおりです。
障害高齢者の日常生活自立度の判定基準
| 生活自立 | ランクJ | 何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 1.交通機関等を利用して外出する 2.隣近所へなら外出する |
|---|---|---|
| 準寝たきり | ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 2.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |
| 寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 1.車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 2.介助により車いすに移乗する |
| ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 1.自力で寝返りをうつ 2.自力では寝返りもうてない |
引用:厚生労働省|「障害高齢者の日常生活自立度」
続いてそれぞれのランクを解説していきます。
ランクJ
ランクJはなんらかの障害はあるが、日常生活はほぼ自立していて、外出も自力でできる状態のことを指します。
さらに、ランクJは外出時の移動距離などにより「J-1」と「J-2」に分かれます。
J-1はバスなどの交通機関を利用し、積極的かつ遠くまで外出できる人が該当します。J-2は近所での買い物や地域行事への参加など、近隣程度であれば外出できる人が該当します。
ランクJのなんらかの障害とは、病気や怪我、それらの後遺症または老衰により生じた身体機能の低下のことをいい、具体的には以下のようなことを指します。
- 脳血管障害による麻痺や失語症
- 下肢筋力低下による歩行状態の衰え
- 老人性難聴によるコミュニケーション時の不自由
ランクA
ランクAは準寝たきりに分類され、いわゆる寝たきり予備軍です。
日常生活の食事、排泄、着替えに関してはほとんど自分でできるが、外出する際は介助が必要な状態のことを指します。
さらに、ランクAは外出時の介助量によって「A-1」と「A-2」に分かれます。
A-1は多くの時間を起きて過ごし、介助があれば比較的長い時間でも外出できる人が該当します。
A-2は日常生活の中で起きている時間は長いが、介助があってもほとんど外出しない人が該当します。
ランクB
ランクBは寝たきりに分類されるグループです。
日常生活において、部分的な介助を必要として、1日の多くの時間をベッド上で過ごしている状態です。
ランクBは「B-1」と「B-2」に分かれています。
B-1は介助がなくても一人で車いすに移乗できて、食事も排泄もベッドから離れて行える人です。
B-2は介助のもとで車いすに移乗し、食事や排泄に関しても介助が必要な人が該当します。
つまりB-1とB-2の分かりやすい違いは、ベッド上で自力で座位を保てるかどうかという点です。
ランクC
ランクCはランクB同様に、寝たきりに分類されますが、ランクBより障害の程度が重い状態を指します。
日常生活の食事、排泄、着替えのいずれにおいても全面的に介助が必要で、1日中ベッド上で過ごします。
ランクCは「C-1」と「C-2」に分かれています。
C-1は常にベッド上で過ごしているが、自力で寝返りができて体位を変えられる人が該当します。
C-2は常にベッド上で過ごしており、自力で寝返りができない人が該当します。
認知症高齢者の日常生活自立度とは
日常生活自立度には障害高齢者だけではなく、認知症高齢者を対象としたものもあります。
ポイントは以下の2点です。
- どの程度自立した生活が送れているか
- 認知症症状から起こるBPSDや中核症状は起きているか
認知症高齢者の場合は、身体機能だけでなく認知症症状の程度によっても日常生活自立度は変わってきます。
また、日常生活自立度はランクによって区別されています。認知症高齢者の判定基準を見ていきましょう。
認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準
認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準は以下のとおりです。
| ランク | 判定基準 | 見られる症状・行動の例 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | |
| Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | |
| Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。 | たびたび道に迷う、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 |
| Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の対応や訪問者との対応など一人で留守番ができない等 |
| Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | |
| Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
| Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ |
| Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ |
| M | 著しい精神状態や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
引用:厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度」
それぞれのランクについて解説します。
ランクⅠ
ランクⅠでは、特に見られる症状や行動の例はありません。
この段階では在宅での生活が基本であり、一人暮らしが可能な状態です。
認知症の進行を予防するために、相談や指導を受けながら症状改善に努めていきます。
また、近所の人の協力など地域連携を活かすことも、在宅での生活を継続するために必要な要素です。
認知症は完治することが難しいため、認知症外来などを利用し、ランクⅠの段階で気づくことが重要と言えるでしょう。
ランクⅡ
ランクⅡも在宅での生活は可能な状態です。
しかし、身の回りのことを上手く行えないなどの症状が出てくるため、一人暮らしは困難と言えます。
また火の不始末やゴミが溜まるなど、日常生活での困難が少しずつ見えてくる時期でもあるので注意が必要です。
常に誰かが見守る必要はありませんが、在宅の介護サービスなどを利用し、定期的に人の介入が必要な段階です。
適切な支援をすることで認知症の進行を予防し、在宅での生活を継続することが重要になってきます。
ランクⅡa
ランクⅡaも在宅での生活が基本です。
しかし、環境が目まぐるしく変わる屋外では、状況を理解することが難しくなります。
よく利用する道でも迷ったり、買い物のときにお金の計算ができなかったりするなどの症状が見られ始めます。
そのため一人での外出は難しく、外出する際は、家族などの支援者が必要になってくるでしょう。
ランクⅡb
ランクⅡbはⅡaの状態が屋外だけではなく、家庭内でも見られる状態のことです。
具体的な例としては、いつも飲んでる薬の管理ができないことや、電話や訪問者の対応が難しく、一人で留守番をすることも困難になります。
この段階では家族の介護のみでも対応でき、在宅での生活も継続可能です。
しかし、誰かが介入していないと身の回りの管理ができないため、家族が仕事などで家を出る際は、訪問介護などの在宅サービスを適宜利用するといいでしょう。
ランクⅢ
ランクⅢは、着替え、食事、排泄などが上手くできない状態で、ランクⅡよりも認知機能が低下した状態です。
一人で日常生活を送ることは難しく、見守りや支援が必要になってきます。
しかし、常に目が離せないわけではないので、在宅生活を継続することは可能です。
専門的な支援が必要になるので、家族の介護のみだと難しい場合も出てきます。
介護サービスなどを利用しながら、日中・夜間ともに適切な支援が受けられる体制を整える必要があるでしょう。
ランクⅢa
ランクⅢaは、ランクⅢの症状が日中に見られる状態のことです。
夜間は落ち着いているため、日中の支援を適切に行うことで在宅生活を継続することは可能です。
日中は徘徊や大声をあげたり、火の不始末や不潔行為を行ったりする場合などもあるので、常時ではないものの多くの時間で見守りや支援が必要になるでしょう。
人の介入が減ることで認知症がより進行する可能性があるため、こまめに介入できる体制を整えていくことが大切です。
ランクⅢb
ランクⅢbは、認知症の程度はランクⅢaと同等ですが、徘徊したり、大声や奇声を出したりするといった症状が夜間を中心に出る場合に該当します。
また夜間に症状が出ることで昼夜逆転の生活になり、健康状態を悪化させやすい段階でもあります。
そのため、ランクⅢaよりも認知機能が低下しやすく、より人の支援や介入が必要です。
家族だけの介護だと負担が大きすぎるため、夜間対応も含めた介護サービスの利用を検討する必要があるでしょう。
ランクⅣ
ランクⅣはランクⅢに比べて、認知症の症状が頻繁に見られる時期で、常時介護を必要とする状態となり、重度の認知症高齢者として対応していきます。
在宅生活が不可能とは言えませんが、意思疎通の困難さが顕著に現れてきます。
在宅の介護サービスだけでは難しく、家族への負担や心身へのストレスが増えていくため、無理に在宅での生活を続ける必要はありません。
積極的に特別養護老人ホームや有料老人ホームなど、施設系の介護サービスを検討しましょう。
ランクM
ランクMでは、以下のような症状が見られます。
- 暴言や暴力行為
- せん妄や幻覚
- 自傷行為など
上記はBPSDと呼ばれ、認知症の進行と心身の不調やストレスなどが重なって現れる症状です。
このような精神疾患が原因で起こる症状は、専門医による治療が必要になります。
これらの症状が見られる場合は、認知症の程度に関係なくランクMが適用されます。
認知症だから仕方ないと思うのではなく、専門機関に相談することが非常に重要です。
高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の活用方法
高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、実際にどのように活用されているか解説します。
要介護度の認定調査
日常生活自立度は要介護認定の判定基準にも用いられています。日常生活自立度を適切に評価することが、要介護認定を決める際に重要になってきます。
要介護度は介護施設の入居条件や、サービスの自己負担額、介護報酬などにもかかわるため、利用者と事業所の双方にとって重要な項目となっています。
認定調査で要介護度の結果を左右する日常生活自立度は、重要な役割であることを知っておきましょう。
介護でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
営業所は安心の365日体制。
お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。
メールは365日24時間受付
受付時間 9:00~18:00
介護サービス計画書(ケアプラン)の作成
日常生活自立度は、利用者の状態を判断する情報として記録されているのはもちろん、ケアプランと言われる介護サービス計画書を作成する際の貴重な判断材料として活用されています。
具体的には、たとえばランクJやA、Ⅰ、Ⅱであれば自立度も高く、利用者本人ができることも多いので「本人が何か役割を持てる」ような支援内容が考えつきます。
一方で、ランクBやC、Ⅲ以上であれば、介助量が多く認知症の症状も重い可能性があるため、利用者本人の負担を少なくするなど、精神的な安定を目的とした支援内容が好ましいでしょう。
日常生活自立度を活用して、利用者の状態に合わせた適切なケアプランを作成することができます。
まとめ
日常生活自立度(寝たきり度)のポイントは以下のとおりです。
- 対象は障害高齢者と認知症高齢者である
- ひとりひとりの状態によってランク別に判断基準がある
- 介護サービス計画書の作成にも活用される
- 要介護度を決める認定調査にも用いられる
- 要介護度は施設の入居条件にも使われる
まずは自身や家族の日常生活自立度を把握し、悪化させないためにどのような介護が有効であるかを考え実践していきましょう。
介護でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
営業所は安心の365日体制。
お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。
メールは365日24時間受付
受付時間 9:00~18:00