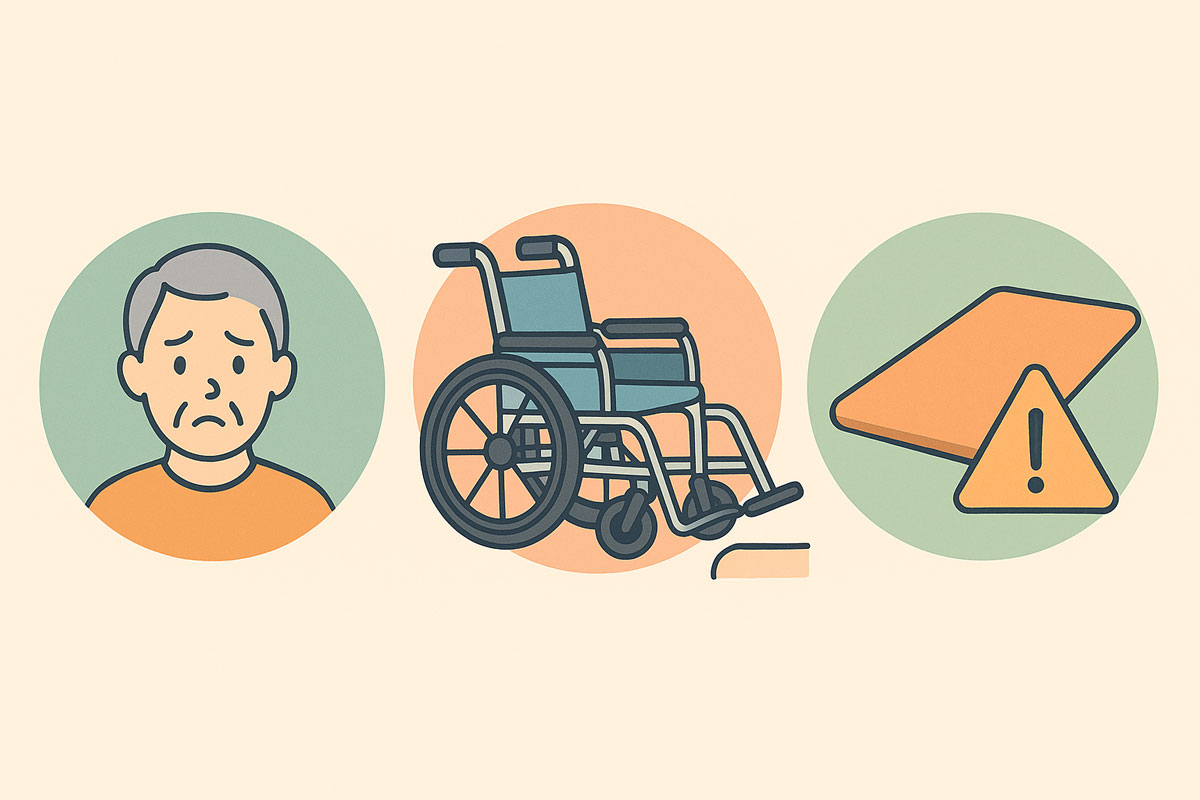更新日:
車椅子の事故を防ぐ方法!安全な生活のために原因と対策を知ろう
車椅子を使用されているご家族の転倒事故に不安を感じていませんか?適切な対策と福祉用具の活用により、転倒リスクを大きく減らせます。
この記事では、車椅子での転倒が起こる原因と具体的な対策、介護保険を活用した福祉用具の利用方法を解説します。
なぜ車椅子での転倒が起こるのか?
車椅子での転倒は、さまざまな要因で起こります。ここでは、事故のパターンや事故が起きやすいシーンについて、詳しく解説します。
車椅子転倒の主な事故パターン
段差を乗り越えようとして前方転倒
よく起きやすい転倒事故の一つに、家の玄関や道路の小さな段差を越えようとしたときに起こります。
例えば、前方に段差があるのに気づかず、車椅子の前輪にタイヤが段差にぶつかるときです。その拍子に、そのまま体が前に倒れ、車椅子から落ちてしまいます。
立ち上がり時に後方へ転倒
車椅子から立ち上がろうとしたとき、両手で手すりに体重をかけながら腰を上げます。このときにブレーキがかかっていないために車椅子から転倒する事故もよく起こります。
カーブ・スロープでバランスを崩す
外出時にスロープを下るときやカーブの道もバランスを崩し、転倒しやすい場面です。
とくに下り坂になっているスロープではスピードが出やすく、ブレーキのない車椅子では止めるのが難しくなります。
さらに、カーブ道だとスピードが出ている分、急なハンドル操作は難しいでしょう。脱輪したり、人にぶつかったりした衝撃で、転倒しやすくなります。
転倒事故が起きやすいシーン
転倒事故は、次のような場所で起こりやすいといえます。
- 自宅での生活の中
- 施設での移乗・移動時
- 屋外での段差・傾斜・段差未整備の道
自宅での生活中
自宅では、玄関の段差やお風呂場、トイレなど部屋の中の段差が危険な場所があります。部屋に敷いている絨毯も小さな段差となるため、転倒しやすい原因の1つだといえます。
また、住宅環境や家具の配置で、通路が狭くなっている場所も要注意です。
施設での移乗・移動時
デイサービスや病院などの施設では、ベッドから車椅子、車椅子からトイレに移る機会が多く、事故が起こりやすくなります。
多くの利用者がいる環境では、どれだけスタッフが気をつけていても、事故が起こることもあるでしょう。
また、施設の床がぬれていたり、普段使っている車椅子と違うタイプだったりすることも事故の原因になります。
屋外での段差・傾斜・段差未整備の道
外出時は最も転倒の危険が高い環境だといえます。歩道の段差、排水溝の隙間、坂道など、転倒の危険が多くなります。
特に雨の日は道路が滑りやすく、普段は事故が少ない場所でも事故が起こりやすくなるでしょう。
また、すべての道が舗装されているわけではありません。未舗装の道路や古い建物では、車椅子がスムーズに通れない環境が多いといえます。
車椅子転倒の原因
車椅子での転倒は、次のような原因が考えられます。
- 利用者本人の要因
- 車椅子の選び方・調整ミス
- 環境・介護側の要因
これらの原因が複数重なる場合もあります。原因を知ることで転倒の予防につなげましょう。
利用者本人の要因
利用者の体の状態が変化したときも転倒が起きる原因の1つです。加齢や病気の影響で筋力が低下すると、車椅子の上で姿勢を保つのが難しくなります。
腹筋や背中の筋肉が弱くなると、お尻が前にずれてしまい、そのまま滑り落ちるリスクが高くなるでしょう。
認知症で注意力の低下、危険への判断力などが衰えることも転倒につながります。
なお、自分で車椅子の操作ができる方でも、ブレーキのかけ忘れやフットサポートで足を引っ掛ける、狭い場所で方向転換をしようとするなど、無理な操作をする場合もあります。一人で操作できる方でも、事故が起きないか見守りが必要です。
関連記事:車椅子の正しい介助方法!よくあるシチュエーションの介助方法を解説
車椅子の選び方・調整ミス
利用者の体に合わない車椅子を選んでいる場合も事故が起きるリスクが高くなります。
車椅子、座る部分の幅や奥行き、床と座面までの高さなどが適切でないと、体が安定せず、適切な姿勢を保てません。
長時間車椅子を使用する場合、座面が硬すぎると姿勢が崩れやすくなります。クッションを使用して車椅子から落ちないようにしましょう。
また、フットサポートがうまく上がらなかったり、ブレーキの効きが悪かったりすることも危険です。車椅子を使用する前には、車椅子に不備がないかチェックしておくことも大切です。
関連記事:車椅子の名称と役割とは?種類と特徴・対象者も解説!
環境・介助側の要因
車椅子の転倒には、環境や介助方法にも影響を受けます。介助者からの声かけが不十分だと、急な動きに利用者が驚いて、介助者の予期しない動きをして転倒する場合があります。
また、ベッドやトイレから車椅子に移る際は、介助者の適切なサポートが重要です。
ベッドや車椅子ストッパーがかかっているか確認し、介助者と介助される方のタイミングを合わせながら移乗介助をしましょう。
車椅子の置く位置や介助するスペースが確保されているかなど、移乗しやすい環境か確認してから介助をするようにしてください。
車椅子での転倒を防ぐ対策
車椅子での転倒は、適切な対策をすることで、減らすことが可能です。
- 正しい姿勢を保つための調整
- 環境整備
- 安全な介助方法の習得
次から、詳しく解説します。
正しい姿勢を保つための調整
転倒を防ぐためには、利用者が正しい姿勢を保てるよう調整することが不可欠です。
クッションやバックサポートを活用し、安定した座位を確保しましょう。クッションやバックサポートはお尻のずれを防ぎ、体幹をサポートするため重要です。
また、フットレストの高さは、足の裏がフットサポートに乗るように調整をします。フットサポートの位置が高すぎると太ももが浮いて不安定になり、低すぎると床に足が引っかかる原因になります。
身体に合わない車椅子は、無理な姿勢を続けることになり、転倒リスクを高めます。利用者の身体に合った車椅子かどうか、定期的にサイズの見直しや点検をしましょう。
環境整備
車椅子の利用者が安全に過ごせるよう、周囲の環境整備は欠かせません。
自宅に段差にスロープを設置して段差を解消し、可能な限りバリアフリー化を進めましょう。小さな段差でも車椅子にとっては大きな障害となり、つまずきや転倒の原因になります。
また、床材にも注意が必要です。お風呂やキッチン・階段などの滑りやすい場所には、滑り止めマットを敷くなどの対策をしましょう。
立ち上がりや移動がしやすいように手すりを設置することも有効な対策の1つです。
手すりがあれば、利用者が一人で移動してもバランスを取りやすくなります。手すりを適切な位置に設置することで、介助者の負担軽減にもつながるでしょう。
安全な介助方法の習得
介助者は、安全な介助方法を習得する必要があります。
とくに、立ち上がりや移乗時のサポート方法は重要です。例えば、利用者の身体状況を詳しく知ることも大切です。なるべく体を密着させ、重心を落とした姿勢を意識したサポートを心がけましょう。
介助中の声かけの合図とタイミングも大切です。「これから立ち上がります」「車椅子に移りますよ」など、具体的な声かけをし、利用者に協力してもらいましょう。
さらに、一人で無理をさせないための工夫も必要です。利用者が疲れていると感じたら、無理に移動を促さず休憩を挟むなど、柔軟な対応を心がけましょう。
福祉用具を活用して転倒を防止しよう
転倒リスクを軽減するためには、日常生活に福祉用具を取り入れることが有効です。福祉用具があれば、利用者が安全に移動できるだけでなく、介護者の介助負担も軽減できるでしょう。
転倒防止付き車椅子
転倒防止付き車椅子とは、転倒防止機能が備わったタイプの車椅子です。例えば、ティッピング防止バーなどがついているタイプです。これは、車椅子の後ろ側に伸びているバーで、後方への転倒を防ぐ役割をしています。
誤操作による転倒を防ぐために、安全センサーや自動ブレーキ機能が搭載されたものもあります。これらの機能を活用すれば、利用者の安全性を高められるうえに、介助者の負担も軽減できるでしょう。
とまっティ 自走
とまっティ自走は、利用者が立ち上がると自動的にブレーキがかかります。万が一、ブレーキをかけ忘れて移乗しても車椅子が移動するのを抑え、後方への転倒防止に役立ちます。
| サイズ | 本体:幅53×奥行100×高さ88.5cm 座幅:40cm/座面高:43.5cm |
|---|---|
| 重量 | 18.1kg |
| 料金(非課税) | ・介護保険利用時 負担額:700円/月 ・レンタル料:7,000円/月 ・販売価格:166,000円 |
電動車椅子
自力での操作に不安がある方や、長距離の移動が多い方には電動車椅子がおすすめです。電動車椅子は、モーターの力で走行するため、坂道や不整地でも安定した走行が可能です。
電動車椅子は傾斜に強く、上り坂の後方への転倒リスクや、下り坂で速度が出すぎるリスクを抑えられます。
ミライト・ウイング
ミライト・ウィングは、グリップを握り、介助者の進行方向に合わせてグリップを押し引きして操作できます。上り坂は楽にのぼれ、下り坂では設定の3分の1の速度に減速するため安定したペースで走行できます。
| サイズ | 本体:幅50×奥行98.5×高さ88cm 座幅:40cm/座面高:43.5cm |
|---|---|
| 重量 | 17.7kg(バッテリー含む) |
| 料金(非課税) | ・介護保険利用時 負担額:2,000円/月 ・レンタル料:20,000円/月 ・販売価格:360,000円 |
滑り止め付きクッション
座っている姿勢が不安定になることで、転倒するケースも少なくありません。そこで役立つのが、滑り止め付きクッションです。
座位保持が難しい方や、前傾姿勢になりやすい方には効果的です。また、高反発素材や低反発素材があり、体圧分散効果も期待できます。
ピタシートクッション ブレス
ピタシートクッションブレスに使用されている立体格子状のジェルは、弾力性があり、体圧を分散します。横揺れがなくずれる力も吸収します。
| サイズ | 幅40×長さ40×厚さ6.5cm |
|---|---|
| 重量 | 1.4kg |
| 料金(税込) | ・介護保険利用時 負担額:202円/月 ・レンタル料:2,020円/月 ・販売価格:22,000円 |
介護保険を利用すれば自己負担は1~3割に
車椅子といった福祉用具を購入すると、高額になることも少なくありません。しかし、介護保険を利用すれば、福祉用具をレンタルすることも可能になります。
福祉用具をレンタルすることで、支払う自己負担額を1割(一定の所得以上の方は2割〜3割)に抑えられます。
福祉用具のレンタル・購入に介護保険を利用するには、要介護認定を受ける必要があります。転倒防止のために福祉用具の活用を検討している方は、まずは市区町村の窓口で相談してください。
介護保険を利用できる介護用品
介護保険を利用してレンタルできる介護用品は、以下のとおりです。
- 車椅子
- 車椅子付属品
- 特殊寝台(介護用ベッド)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分は除く)
- 自動排泄処理装置(要介護度4・5が対象)
転倒を予防するための介護用品のほか、利用者の身体の状態に合わせて、さまざまな福祉用具が用意されています。
利用を検討している方は、ケアマネジャー、または指定された福祉用具販売事業者にお問い合わせください。
介護保険を利用してレンタルする流れ
介護保険を利用して福祉用具をレンタルする流れは以下の通りです。
- 市区町村で要介護認定を申請
- ケアプランの作成
- 福祉用具貸与販売事業者の選定
- 福祉用具貸与販売計画の作成
- 利用者・家族への説明・同意・契約
- 利用開始
まずは、市区町村の窓口で要介護認定の申請を行います。認定後、ケアマネジャー(介護支援専門員)が利用者の心身の状態や生活環境に合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づいて、ケアマネジャーが紹介する福祉用具貸与販売事業者が自宅を訪問し、利用者の状態や住環境を確認したうえで、必要な福祉用具を選択します。納得したうえで契約を結びましょう。
契約後、福祉用具が自宅に搬入され、利用開始です。レンタル開始後も定期的に使い方や使い心地を確認します。必要に応じて、調整や変更が行われます。
まとめ
車椅子での転倒事故は、適切な知識と対策により予防できます。転倒が起こりやすい場所は、段差や坂道などです。
また、車椅子のブレーキがかかっていなかったり、移乗する際のスペースが確保できていないなど、介護者の不注意や環境によっても転倒が起こりやすくなります。
転倒の事故は福祉用具を活用することで防ぐことが可能です。介護保険を活用すれば、利用者の安全性を高め、経済的な負担も軽減できるでしょう。
利用者が安心して生活を送るために、検討してみましょう。まずは、市区町村の窓口やケアマネジャーに相談してください。