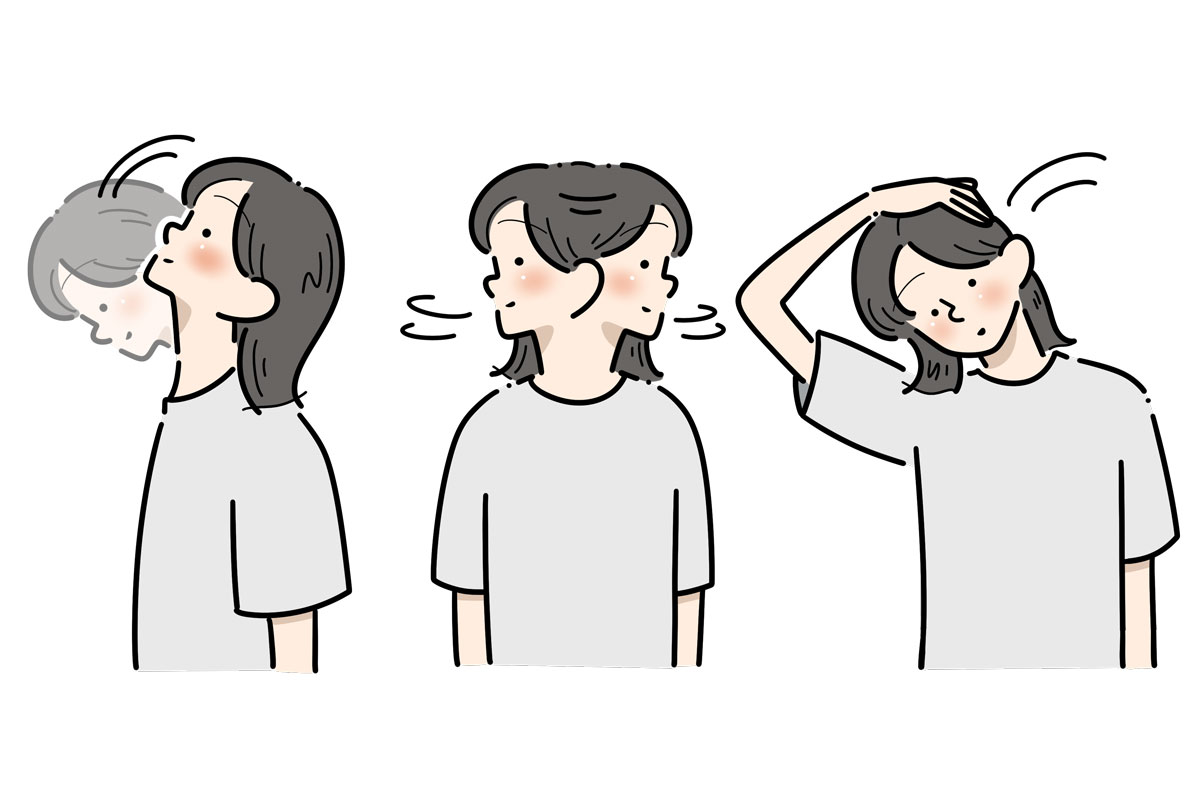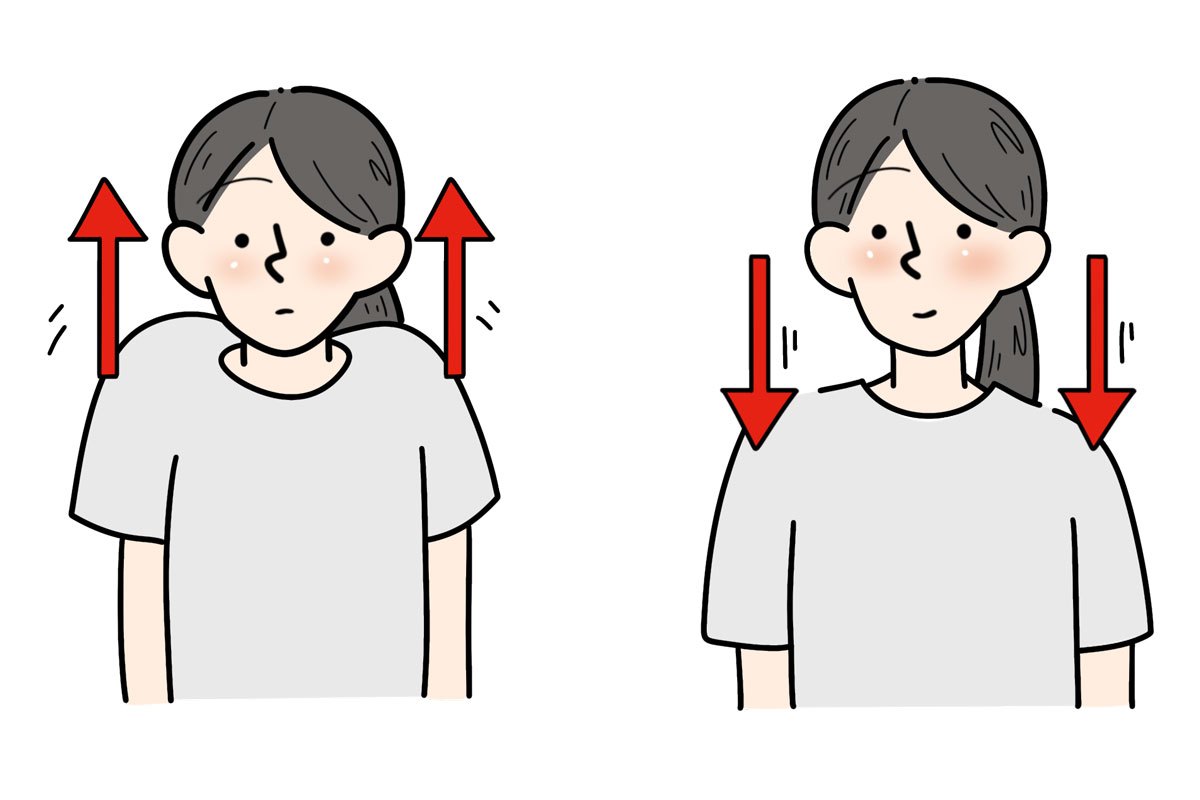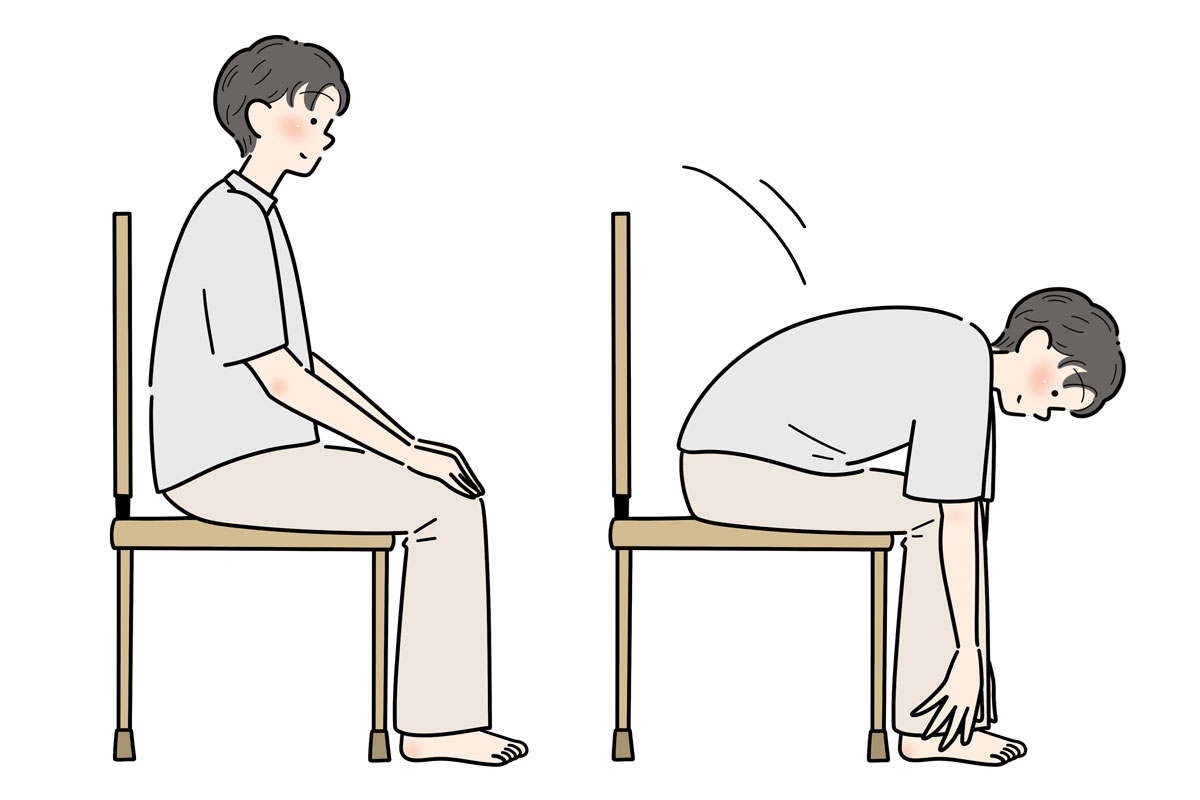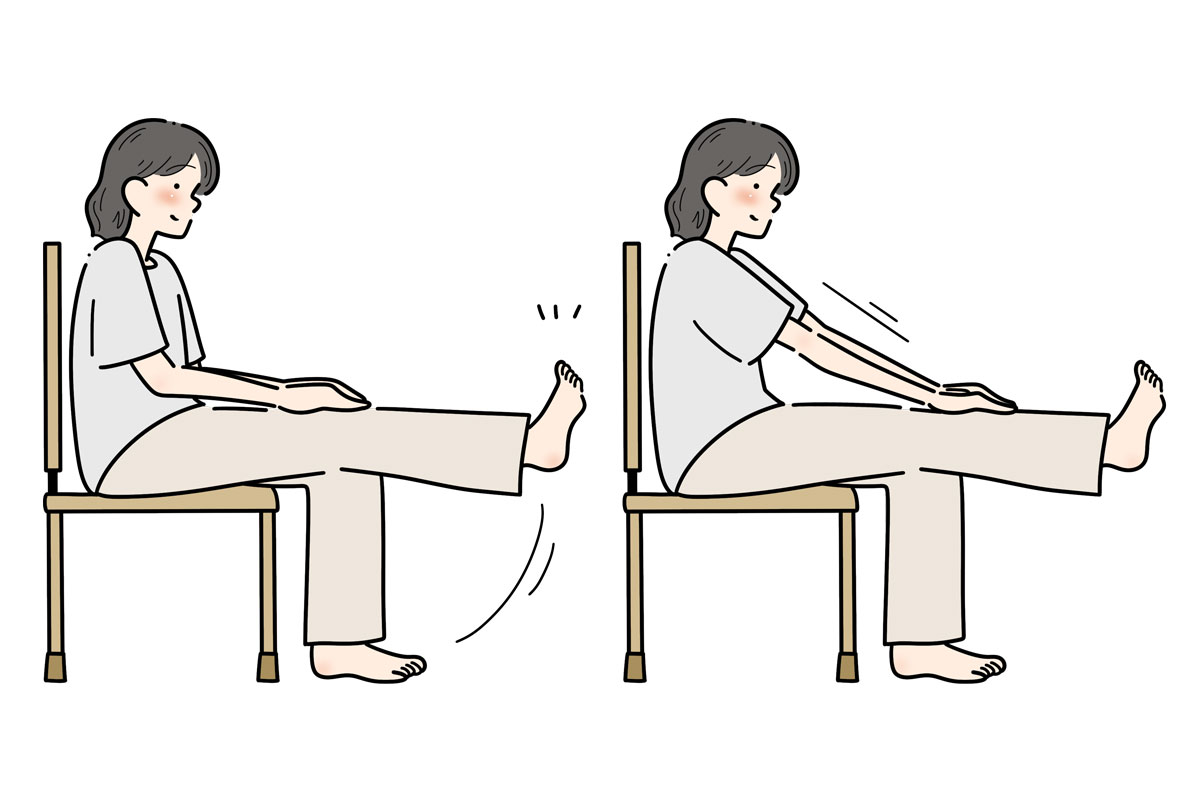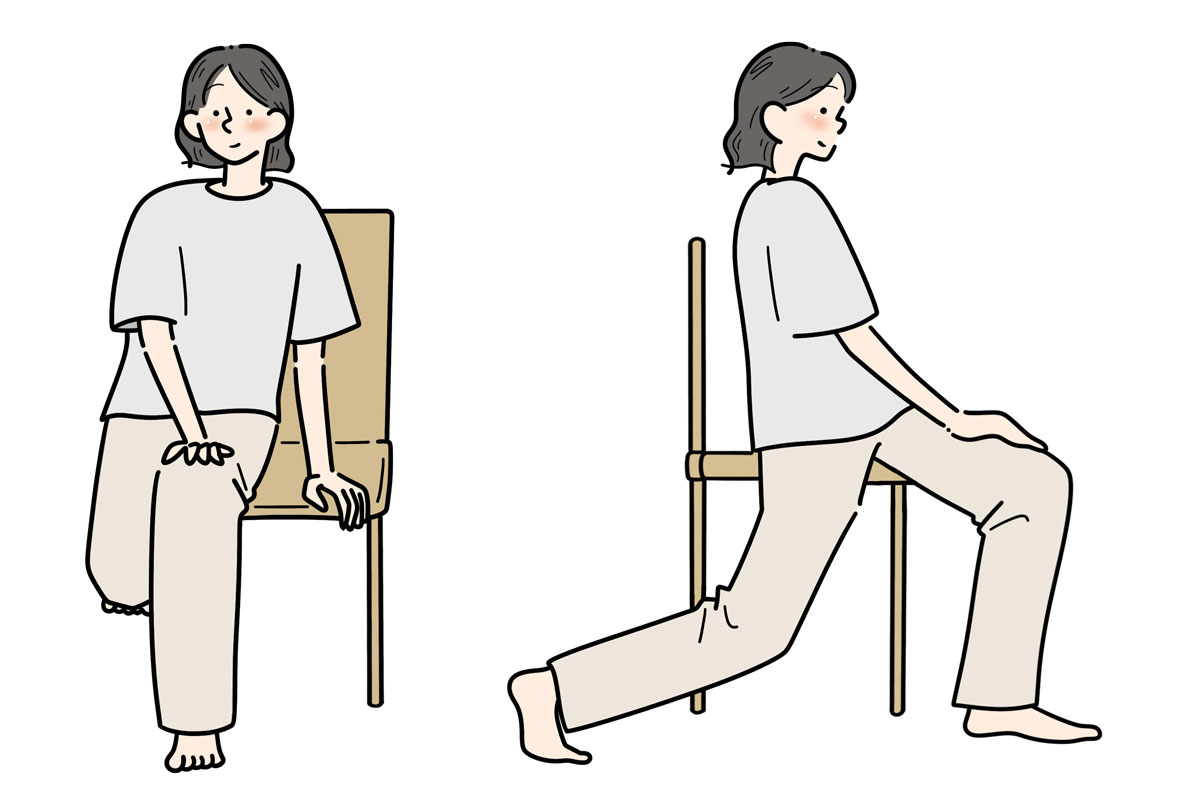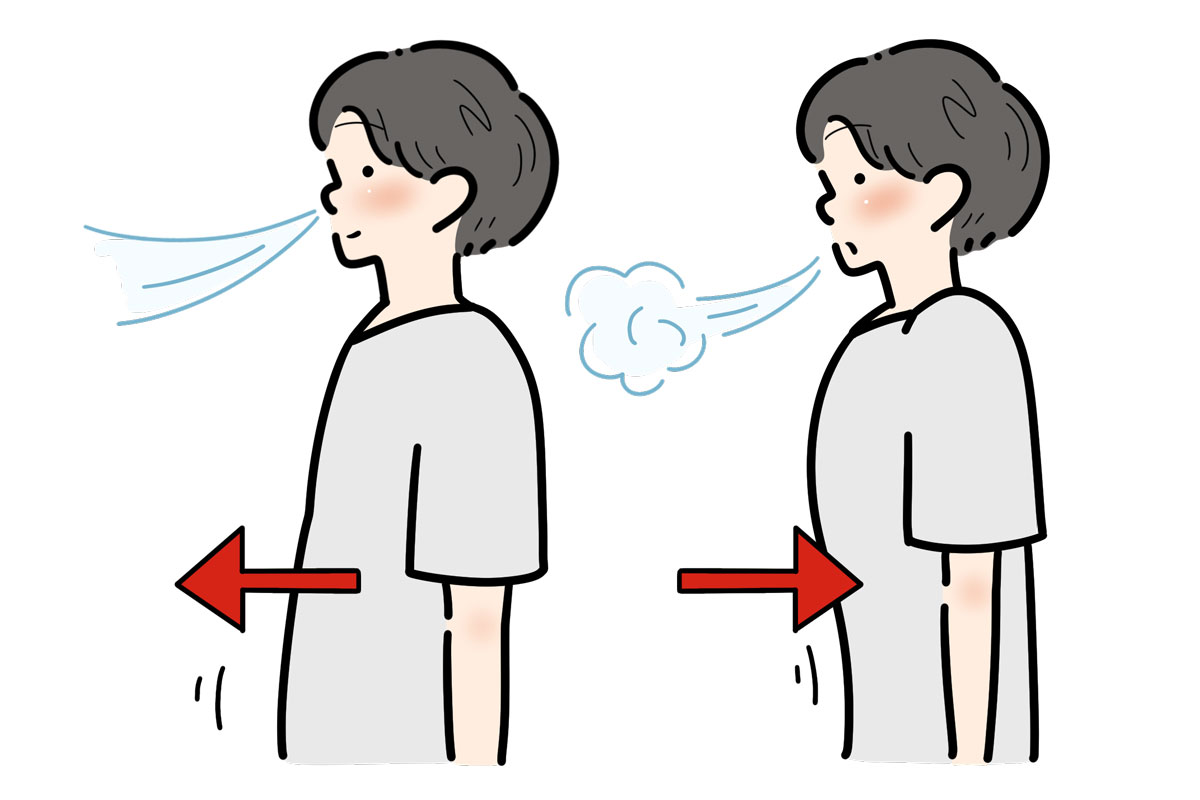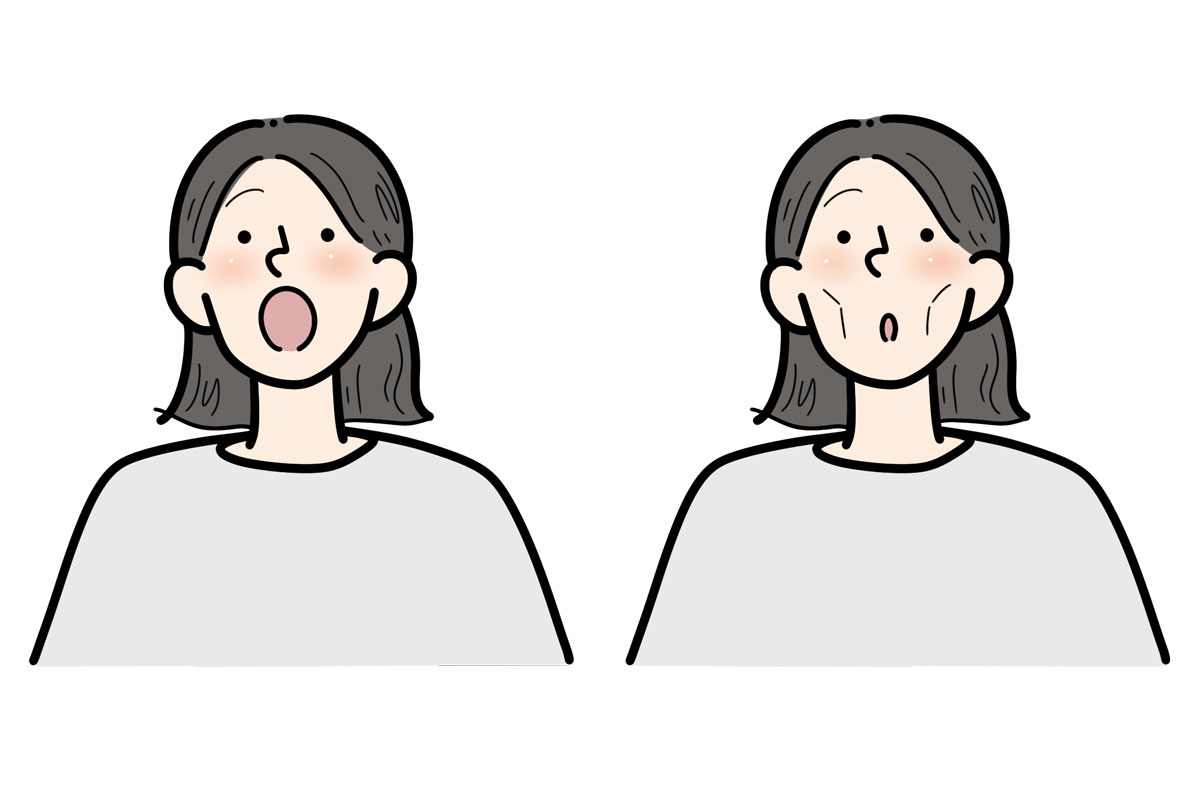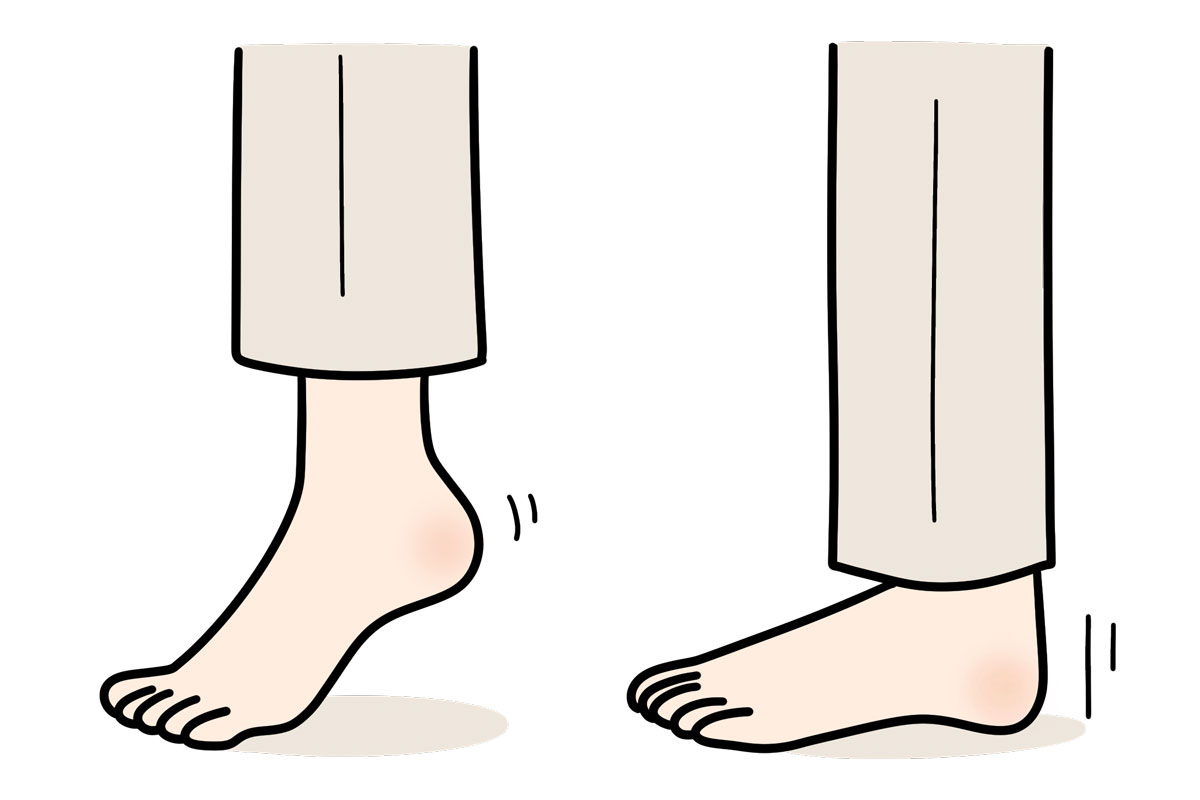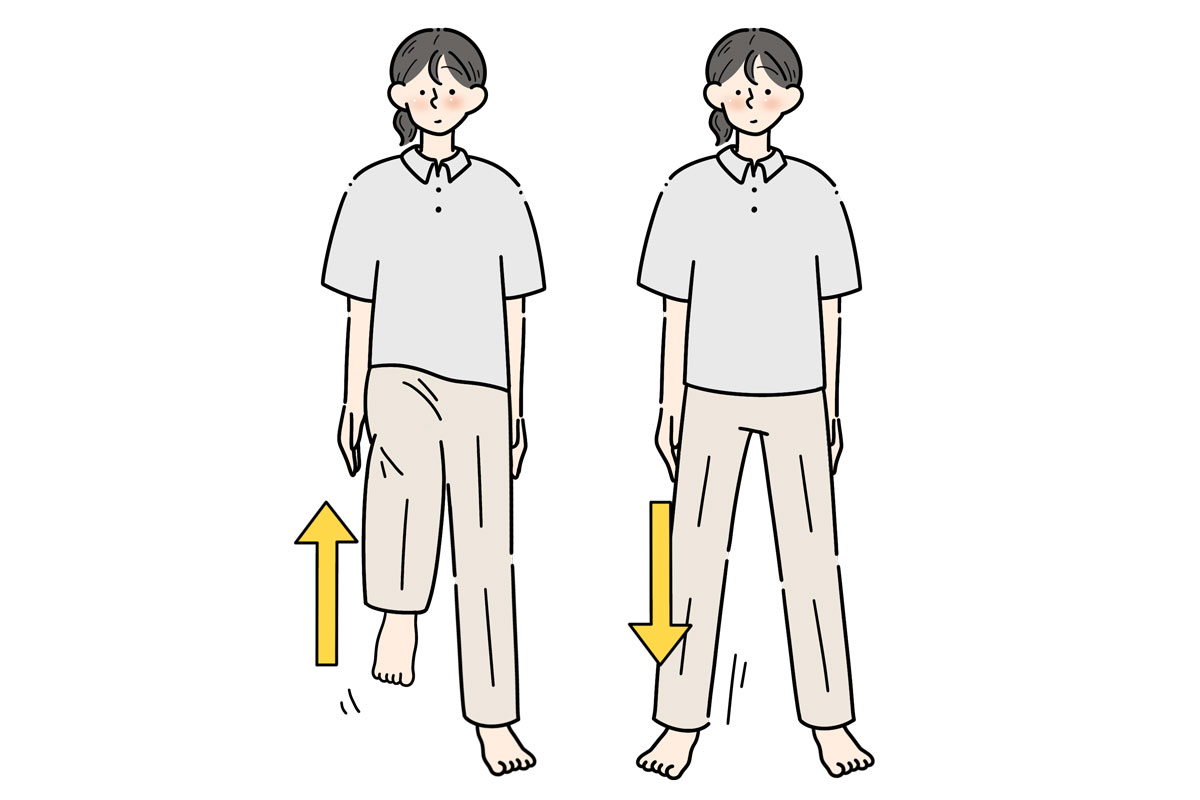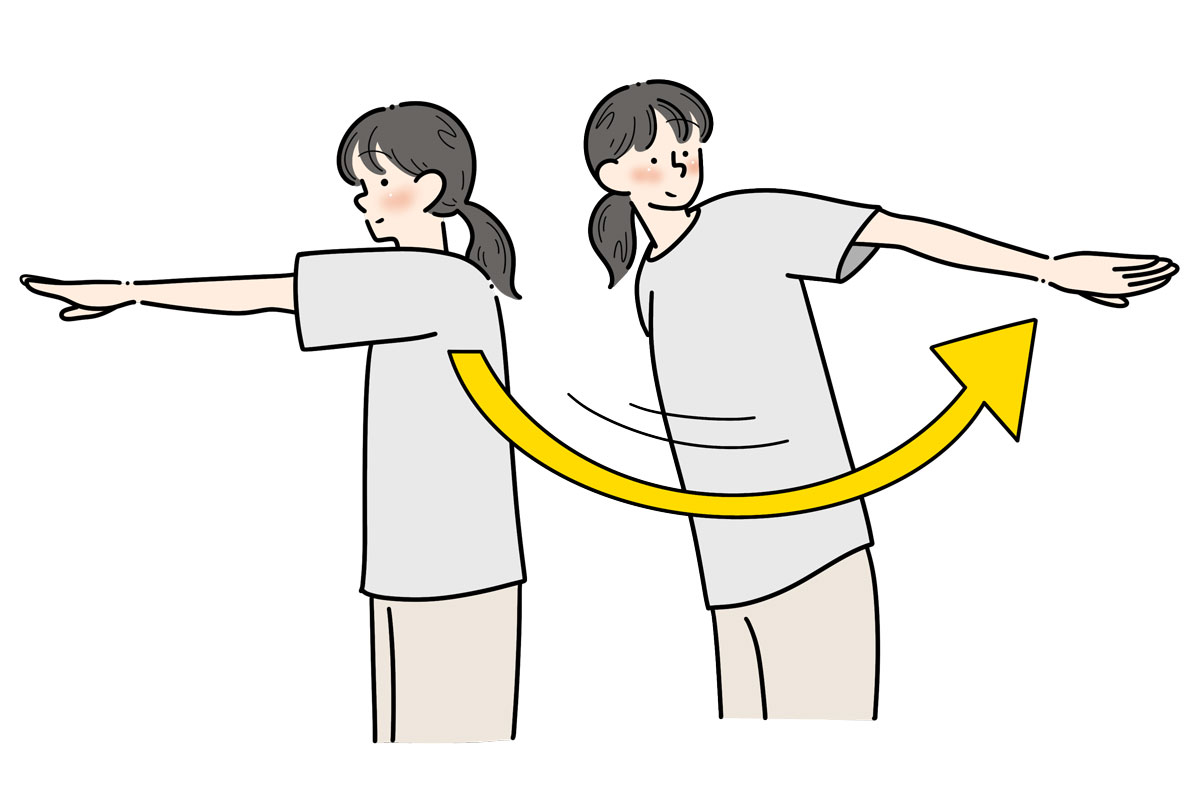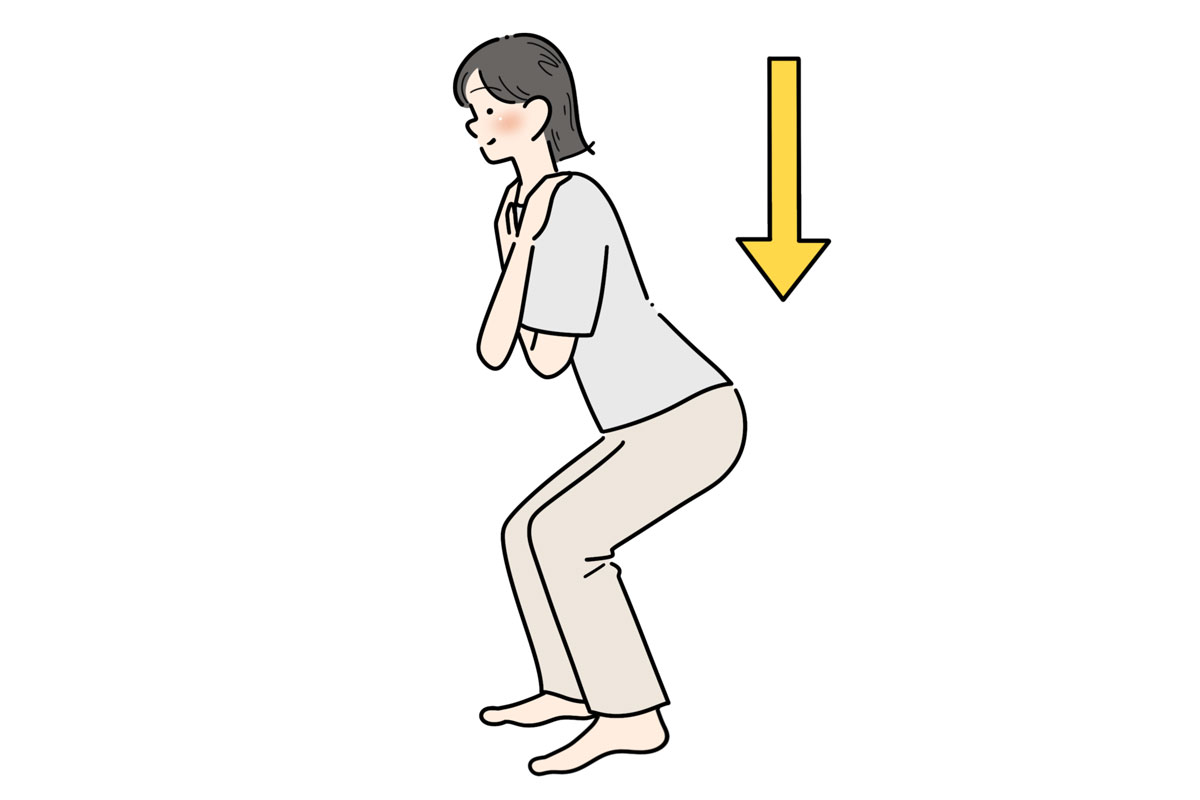更新日:
高齢者の体操には何がある?中止基準や楽しく安全に行うポイントも解説!
高齢者が行う体操は、心身の機能を維持・向上させ、意欲的な生活を送るための大切な活動です。
本記事では、高齢者が行う体操を「座ってできるもの」と「立って行うもの」に分けて紹介します。
また、体操のもつ役割や運動の中止基準、安全に行うポイントなどもあわせて解説していきます。
高齢者向けに体操を実施する方は、参考にしてください。
座ってできる体操
座ってできる体操には、首・肩・腰など上半身の運動があります。
座って行うため、安全に実施できる点が特徴です。
首の運動
首の運動には、以下3種類の動きがあります。
それぞれ10回ほど行いましょう。
- 前後に倒す
- 左右を向く
- 左右に倒す
期待できる効果は以下のとおりです。
- 肩こりの予防
- 噛む・飲み込む力がつく
- バランス能力を保つ
- 首の筋肉がゆるんで動く範囲が広くなる
首を動かすと頭の位置が変わるため、痛みやめまいを起こす方もいます。
無理せずゆっくり行いましょう。
肩の運動
肩まわりの筋肉をほぐし、動く範囲を広げる運動です。
着替えや入浴時の洗体・洗髪などが楽に行えるようになります。
肩は関節が球状になっているため、前後・上下・左右といろいろな方向に動きます。
運動は以下のように行いましょう。
- 肩の上げ下げ(すくめてストンと落とす)
- 肘をまわす(弧を描くように大きく)
それぞれ10回ほど行います。
腰の運動
背中・腰・股関節の柔軟性が改善され、靴や靴下の脱ぎ履きが楽にできるようになります。
また、腰痛予防の効果も期待できます。
以下の順に行いましょう。
- 両手を太ももにおく
- 両手を膝・足首へと滑らせながら身体を曲げる
腰や背中の筋肉が伸びているのを感じることが大切です。
ゆっくりと20秒ほどを目安に行いましょう。
【参考】
e-ヘルスネット ストレッチングの実際
太ももの運動
太ももの裏にある「ハムストリングス」という筋肉をストレッチする運動です。
腰痛や神経痛の改善が期待できます。
以下の順に行いましょう。
- 椅子に座って片足を伸ばし、つま先を上に向ける
- 身体を起こしたまま、両手を膝からすねに向かって伸ばしていく
腰痛や、足に電気が走るような痛みが出た場合は、中止してください。
捻りの運動
捻りの運動には、腰や背中がやわらかくなる効果があります。
歩行中に急に引き返したり、トイレの水洗レバーを操作したりするときのバランスがとりやすくなります。
身体を左右に捻りながら、両腕を一緒にまわしましょう。
いっぱいまで捻じったところで20秒姿勢をキープします。
脇腹の運動
脇腹の運動は、姿勢の改善や呼吸機能の維持・向上が期待できます。
以下のように左右行いましょう。
- 右手を上げながら左に身体を倒す
- 左手を上げながら右に身体を倒す
脇腹から腰の付近が伸びているのを確認しながら、20秒ほど伸ばします。
股関節の運動
股関節の運動では、足のつけ根にある腸腰筋をよく伸ばしておきましょう。
腸腰筋がやわらかくなると、姿勢や腰痛の改善が期待できます。
以下の順に行いましょう。
※右の腸腰筋を伸ばす場合
- 椅子の右端に座り、右足を後ろへ伸ばす
- 左足は膝を曲げ、足の裏全体を床につける
- 身体をまっすぐに起こしたまま、骨盤を後ろに倒すようにする
20秒ほどを目安に行いましょう。
深呼吸の運動
深呼吸の運動では横隔膜が鍛えられ、腹式呼吸を意識すると腹筋にも効果があります。
腹筋が鍛えられると、姿勢の安定や腰痛予防につながります。
以下の順に行いましょう。
- 鼻からゆっくりと息を吸い込みながら、おなかを膨らませる
- 口からゆっくりと息を吐きながら、おなかをへこませる
10回ほどを目安に行ってください。
口腔体操
口・頬・舌・のどの筋肉を鍛え、以下の機能に効果があります。
- 咀しゃく(噛む)
- 嚥下(飲み込む)
- 表情をつくる
- 会話を楽しむ
以下の体操を行いましょう。
- 口を開けしめする
- 口をすぼめた後、横に引く
- 頬を膨らませたりすぼめたりする
- 舌を出し入れしたり、口の中で舌をまわしたりする
- 「パ」「タ」「カ」「ラ」をくり返したり「パパパ」「タタタ」など発音したりする
それぞれ10回ほど行ってください。
立って行う体操
立って行う体操では、主に足と体幹(胴体)の筋肉を鍛え、転倒予防の効果が期待できます。椅子や机を用意し、軽く手を添えて行いましょう。
ふくらはぎの運動
歩くときに足で蹴り出す力や、身体をまっすぐに起こす力をつける運動です。
以下の順に行いましょう。
- 足を肩幅にひらく
- 両方の踵を軽く上げ下ろしする
- 慣れてきたら、勢いよく上げてからゆっくり下ろす
3と4はそれぞれ10回ほど行います。
身体を前に倒さず、まっすぐ起こして行うのがポイントです。
軸足の運動
上がっていない方の足に体重をかけ、軸足として支える練習です。
左右の体重移動が円滑になり、片足で立つバランスが向上します。
以下の順に行いましょう。
- 足を肩幅にひらく
- 片足を小さく5回上げて下ろし、もう片方も同様に行う
- 慣れてきたら大きく5回上げて下ろし、もう片方も同様に行う
3は下ろす際、床につま先がほとんど触れないようにしましょう。
体幹の運動
体幹の運動には、胴体の柔軟性が改善し、歩くときに腕を振りやすくする効果があります。
以下の順に行いましょう。
- 腰より少し広く足をひらく
- 片手を前に伸ばし、上げた手を後ろにまわしながら手の方に振り向く
- 8カウントで1回とし、左右2回ずつ行う
手の動きを意識しすぎて、体幹の動きが小さくならないようにします。
身体全体で手を追いかけるように、行いましょう。
スクワット
スクワットは、太ももの前と後ろの筋肉や、足全体を効率的に鍛える運動です。
以下の順に行いましょう。
- 足を腰の幅ほどにひらく
- 「1、2、3、4」で膝を曲げ、「5、6、7、8」で伸ばす
膝を曲げるときはお尻を後ろに引きながら行います。
一方で、伸ばすときは足全体で身体を押し上げるように踏ん張りましょう。
足踏み・踵上げの運動
足踏みは、股関節の前側にある「腸腰筋(ちょうようきん)」を鍛える運動です。
歩くときの足を上げるのを助け、転倒予防につながる効果があります。
また、姿勢をまっすぐに保ち、背骨の正常なS字カーブをつくって腰痛予防にもなります。
左右の足を交互に「1、2、3、4」で小さく、「5、6、7、8」で大きく足踏みしましょう。
8までカウントして1回とし、2回行います。
体操のレクリエーションが重要な理由
高齢者にとって体操のレクリエーションが重要な理由は、以下の目的があるからです。
- 運動習慣を身につける
- 他者との交流をとおして孤立感を解消する
- 日常生活に楽しみを見出す
高齢になると身体の機能が衰えやすくなります。
適度な運動習慣を身につけることで、身体機能の維持・向上が期待できます。
体操のレクリエーションは、集団で行うものです。
他者とはげましあって行うと連帯感がうまれ、集団に溶け込みやすくなります。
そして日常生活に楽しみを見出すことで、意欲的な生活が送れるようになります。
このように体操のレクリエーションには、心・身体・社会生活といったさまざまな側面から、高齢者の健康を保つ重要な役割があるのです。
体調によっては体操を行ってはいけない場合もある
体調によっては、体操を行ってはいけない場合もあります。
「アンダーソン・土肥の基準」という運動の中止基準を紹介します。
【運動を行わない方がよい場合】
- 安静時脈拍数が120回/分以上
- 上の血圧が200mmHg以上
- 下の血圧が120mmHg以上
- 労作性狭心症がある(動くと胸が痛む・苦しい)
- 心筋梗塞を起こしてから1ヶ月以内
- うっ血性心不全の所見が著しい不整脈がある
- 心房細動以外の著しい不整脈がある
- 運動前からすでに動悸・息切れがある
【途中で中止する場合】
- 中等度の呼吸困難、めまい、吐き気、胸の痛みなどが出た
- 脈拍が140回/分以上
- 1分間に10回以上の期外収縮が出る、または頻脈性不整脈(心房細動、上室性または心室性頻脈)あるいは徐脈(50回未満/分)が出た
- 上の血圧が40mmHg以上、または下の血圧が20mmHg以上上昇した
【一旦中止して回復してから再開する】
- 脈拍数が運動時の30%をこえた、ただし2分間の安静で10%以下に戻らない場合は中止するか極めて軽い運動に切り替える
- 脈拍数が120回/分をこえた
- 1分間に10回以下の期外収縮が出た
- 軽い動悸や息切れを訴えた
上記の基準を守らずに運動を続けると、体調の悪化を招く恐れがあり、場合によっては生命の危険にもつながってしまいます。
必ず基準を守り、安全に体操を楽しみましょう。
体操を楽しく安全に行うポイント
体操を楽しく安全に行うためには、いくつかのポイントを押さえておきましょう。
高齢者によってできる動きは異なるため、椅子やテーブルを用意し、レベルに合わせた内容や環境の準備が大切です。
また、アップテンポの音楽を流すことで気持ちを高め、意欲的に行えるよう配慮します。
服装は、ジャージやスウェットなど伸縮性のある物を着用し、運動靴を履いて行いましょう。
このように、楽しく安全に行える配慮が大切です。
まとめ
高齢者の体操にはさまざまなバリエーションがあります。
体操のレクリエーションは、運動習慣を身につけることだけが目的ではありません。
他者との交流を促進し、心身ともに健康的な生活を送る意味もあります。
一方で、体操は一定の基準に合わせて行わないと、体調を崩す恐れがあります。
楽しく安全に行える配慮が、高齢者の体操には重要です。