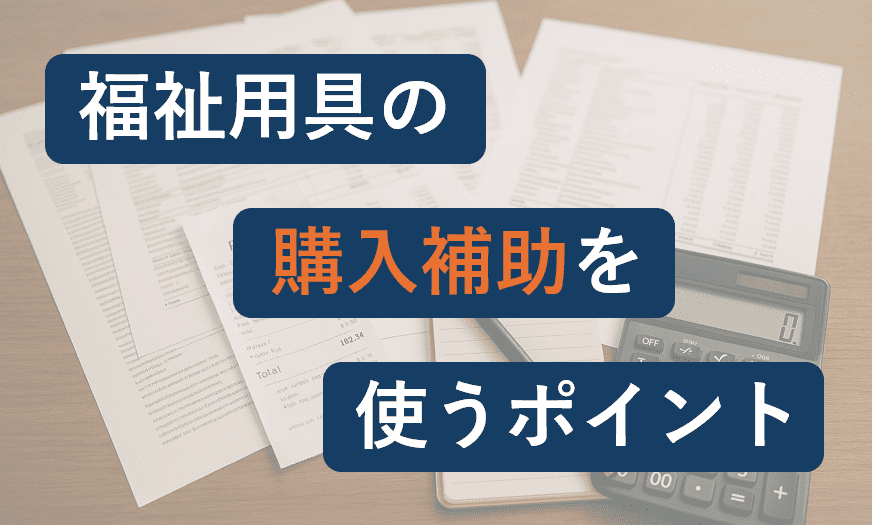更新日:
福祉用具の購入補助を使うポイント
在宅介護で必要となる入浴・排泄・移乗の道具は、購入時に自己負担を抑えられる制度があります。対象や手続きの流れをつかみ、自治体のルールに合わせて書類をそろえれば、必要なタイミングで無理なく導入できるでしょう。ここでは枠組みから申請、代表的な対象用品までを整理します。
購入補助の枠組み
「特定福祉用具販売(介護保険)」を中心に、自治体の独自助成が加わる場合があります。まずはどの制度が使えるかを確認しましょう。
特定福祉用具販売
原則として要支援1〜要介護5の認定を受けた方が対象です。品目は腰掛便座/入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽手すり等)/簡易浴槽/自動排泄処理装置の交換部品 などと定められています。年度(4/1〜翌3/31)ごとに10万円までが上限で、自己負担は1〜3割が目安です。複数品目の組み合わせも可能ですが、必要性(ケアプラン上の位置づけ)が重要になります。
自治体ごとの違い
同じ介護保険でも、事前申請の必須/受領委任払いの可否/必要添付書類などは自治体で差があります。特に受領委任払いは、自己負担分のみの支払いで済むメリットがある一方、登録事業者からの購入が条件になることが多いです。早めにケアマネジャーと役所の窓口へ確認し、購入時期と在庫確保の段取りを合わせておくとスムーズでしょう。
申請と購入の流れ
「見積→申請→承認→購入(納品)→支給申請」の順で進めるのが基本です。受領委任の場合は承認後に自己負担分のみ支払います。
見積取得・申請・納品
まず事業者から型番・数量・金額入り見積を取り、ケアプランと合わせて役所へ申請します。承認後に購入・納品し、領収書原本・カタログ抜粋・設置写真などを添えて支給申請します。償還払いの場合は全額いったん立替え、後日上限内で払い戻しを受けます。納期がかかる用品もあるため、入浴開始・退院日・在宅復帰日に間に合うよう逆算して動くのがコツです。
支給申請・履歴管理
領収書は購入者名=被保険者名で発行してもらい、型番・数量・単価が分かる明細を必ず添付。写真は「設置前後」や「使用環境が分かる」構図で残すと審査が滞りにくいです。更新や再購入の判断に備え、使用開始日・不具合・メンテ履歴も手帳やアプリで記録しておくと良いでしょう。
対象品目
ここでは実際に購入補助の対象となることが多い品目を紹介します。
腰掛便座
和式便器に取り付けて腰掛式に変換するもの、洋式便器に取り付けて高さを補うもの、居室で利用するポータブルトイレまで、様々なものが対象です。
入浴用椅子
背もたれ付きや折り畳み式など、様々な種類があります。身体の状態や浴室の広さにあわせて選定しましょう。
浴槽用手すり
浴槽の縁に固定して出入りを補助します。工具不要で高さ調整できるタイプは設置・撤去が容易で、転倒予防と姿勢保持の両面で効果的です。
まとめ
購入補助は年度上限・対象品目・申請順序を押さえれば、導入のハードルを大きく下げられます。ケアプランで必要性を明確化し、見積・申請・書類管理を丁寧に進めることが成功の近道です。自治体ルールに沿って必要なときに必要な用具を整えていきましょう。