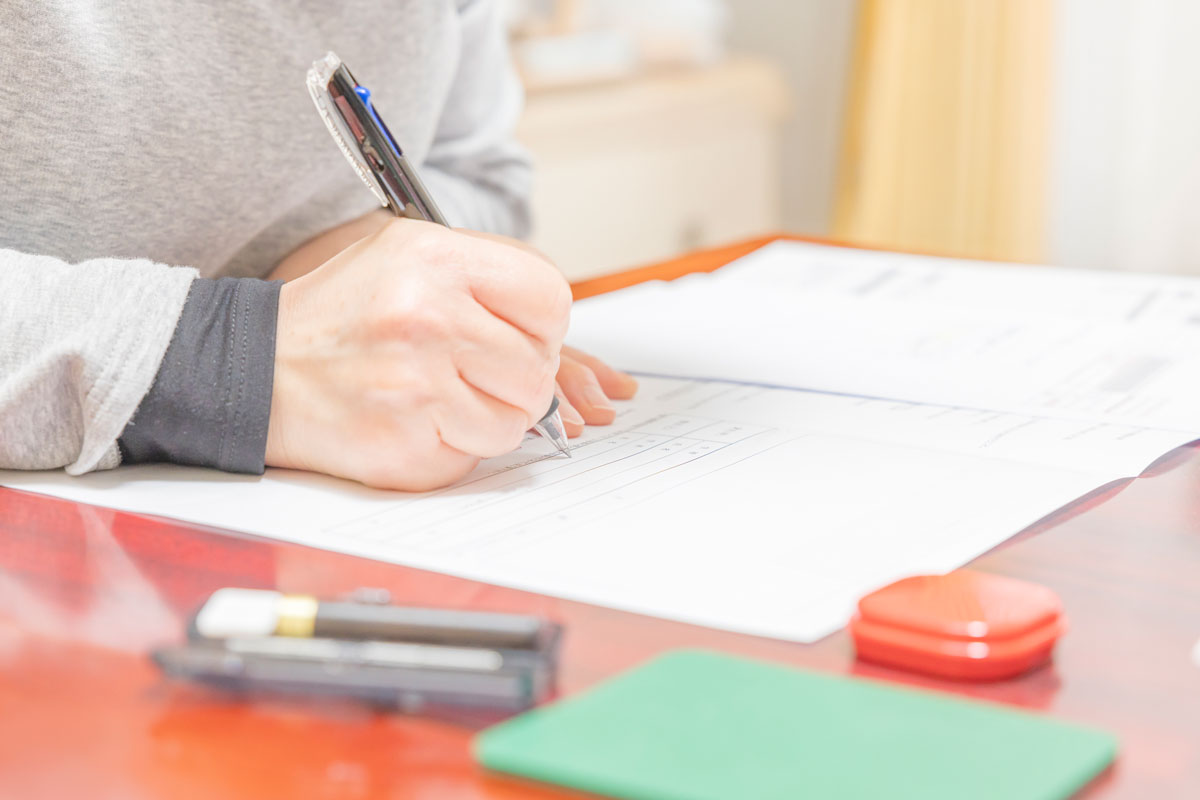更新日:
自立支援医療とは?対象となる障害や申請方法を詳しく紹介
自立支援医療とは、心身の障害を除去・軽減するための医療にかかる医療費を、自己負担額を一律1割とする公費負担医療制度です。医師から継続的な治療が必要と判断された場合に利用できます。
しかし、自立支援医療の対象となる障害は限られており、全ての方が利用できるわけではありません。そこで本記事では、自立支援医療の内容から対象となる障害、申請方法等を詳しく解説します。
自立支援医療とは
自立支援医療とは、心身の治療にかかる治療費の自己負担を軽減する制度のことです。
本来、医療費は保険が適用されて3割負担が一般的ですが、自立支援医療制度を利用すれば原則1割になります。
対象者は医師より通院医療を継続的に要すると診断された方、精神疾患による外来治療中の方です。
主に以下の疾患が対象になります。
- 統合失調症
- うつ病
- PTSD
- てんかん
- 知的障害
- パーソナリティ障害など
自立支援医療の対象者
自立支援医療の対象者は、以下のとおりです。
- 更生医療
- 育成医療
- 精神通院医療
それぞれの対象者を紹介します。
更生医療
更生医療は、身体障害者手帳が交付されている18歳以上の人で、症状・障害の治療を行うと効果が期待できる場合に利用できます。
肢体不自由者の関節拘縮であれば、人工関節置換術の費用、視覚障害者の白内障であれば、水晶体摘出術が挙げられます。
育成医療
育成医療は、18歳未満の身体に障害のある児童、または放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、その障害の除去・軽減する治療で効果が期待できるときに利用できます。
支援の対象となるのは、育成医療対象の症状の手術・治療にかかる費用のみです。
育成医療対象外の病気、保険適用外の治療は支援の対象となりません。また、18歳を超えて医療支援を受ける場合は、更生医療になります。
精神通院医療
精神通院医療とは、うつ病や躁うつ病などの精神疾患の診断が降りており、通院をして継続的な治療が必要な人が対象の制度です。デイケアや訪問看護にも、制度が適用されます。
受給者証の有効期限は1年となっており、継続して支援を受ける場合は更新をする必要があります。なお、精神通院医療を利用しているからといった周囲にバレることはありません。
自立支援医療の対象となる障害・治療例
ここでは、自立支援医療の対象となる障害・治療例を以下の3つに分けて紹介します。
- 更生医療
- 育成医療
- 精神通院医療
更生医療
更生医療の対象となる障害とそれに対する治療例は、以下のとおりです。
| 対象となる障害 | 疾患 | 治療例 |
|---|---|---|
| 視覚障害者 | 白内障 網膜剥離 瞳孔閉鎖 角膜混濁 |
水晶体摘出手術 網膜剥離手術 虹彩切除術 角膜移植術 |
| 聴覚障害 | 鼓膜穿孔 外耳性難聴 |
穿孔閉鎖術 形成術 |
| 言語障害 | 外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 | 歯科矯正 |
| 肢体不自由 | 関節拘縮 関節硬直 |
形成術 人工関節置換術 |
| 内部障害 | 先天性疾患 後天性心疾患 腎臓機能障害 肝臓機能障害 小腸機能障害 HIVによる免疫機能障害 |
弁口、心室心房中隔に対する手術 ペースメーカー埋込み手術 人工透析療法、腎臓移植術 肝臓移植術 中心静脈栄養法 免疫調節療法など |
育成医療
育成医療の対象となる障害とそれに対する治療例は、以下のとおりです。
| 対象となる障害 | 疾患 | 治療例 |
|---|---|---|
| 視覚障害者 | 白内障 先天性緑内障 |
角膜移植術、白内障手術など |
| 聴覚障害 | 先天性耳奇形 | 外耳道形成術など |
| 言語障害 | 口蓋裂等 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であり、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 |
形成術 歯科矯正など |
| 肢体不自由 | 先天性股関節脱臼 関節置換術 脊椎側彎症 |
人工関節置換術 理学療法など |
| 内部障害 | 先天性疾患 後天性心疾患 腎臓機能障害 肝臓機能障害 小腸機能障害 HIVによる免疫機能障害 その他の先天性内臓障害 |
人工透析療法 抗HIV療法 免疫調節療法 肝臓移植術 中心静脈栄養法など |
精神通院医療
精神通院医療の対象となる障害は、以下のとおりです。
- 病状性を含む器質性精神障害
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分障害
- てんかん
- 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格及び行動の障害
- 精神遅滞
- 心理的発達の障害
- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
治療法は薬物療法や休養、精神療法が挙げられます。
自立支援医療の利用料
自立支援医療の利用料は、所得区分によって異なります。月額医療費の負担イメージは、医療保険が7割、自立支援医療費(月額医療費-医療保険-患者負担)、患者負担(1割)です。
| 自己負担上限月額 所得区分 |
更生医療 | 育成医療 | 重度かつ継続 | |
|---|---|---|---|---|
| 一定所得以上 | 市町村民税235,000円(年収約833万円以上) | 対象外 | 20,000円 | |
| 中間所得2 | 市町村民税33,000円235,000円未満(年収約400万円~833万円未満) | 総医療費の1割または 高額医療費の自己負担限度額 |
10,000円 | |
| 中間所得1 | 市町村民税33,000円未満(年収約290万円~400万円未満) | 5,000円 | ||
| 低所得2 | 市町村民税非課税(※低所得1を除く) | 5,000円 | ||
| 低所得1 | 市町村民税非課税(本人または障害児の保護者の年収が80万円以下) | 2,500円 | ||
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | ||
参照:緊急に措置すべき事項
自立支援医療の経過的特例
自立支援医療の経過的特例とは、自立支援医療制度対象者の自己負担上限額を2万円とする措置です。本来、自立支援医療制度は、市民町村税の額が235,000円以上の世帯は対象外となっています。
しかし経過的特例によって、市民町村税の額が235,000円以上の世帯かつ、高額治療継続者に該当する方は自立支援医療の対象として、自己負担上限月額が2万円になります。
自立支援医療の経過的特例の期限は令和6年3月31日であったものの、障害者総合支援法施行令の改正によって、令和9年3月31日に延長されました。
自立支援医療の申請方法
自立支援医療の申請は、以下の書類とともに役所窓口で申請認定申告書を記入して、提出する必要があります。
- 診断書
- 健康保険証
- マイナンバーもしくはマイナンバー通知書
- 世帯所得が分かる書類(課税証明書や生活保護受給証明書など)
- 印鑑
なお、上記の書類があれば申請できるものの、自立支援医療受給証はすぐに交付されるものではありません。
手元に届くまで1ヶ月~2ヶ月ほどかかるため、届くまでは申請書の控えで代用しましょう。また、自立支援医療は1年ごとに更新が必要となっており、申請時と同じように障害福祉課窓口で手続きしてください。
まとめ
本記事では、自立支援医療の対象者や申請方法等を詳しく紹介しました。自立支援医療とは、心身の治療にかかる治療費の自己負担を原則1割にする制度です。
対象者は、躁うつ病や統合失調症などの精神疾患、18歳未満・18歳以上の視覚障害者や聴覚障害者などです。自立支援医療を利用すれば、治療にかかるお金の負担を少しでも軽くしてくれるため、経済的に困っている人はぜひ利用したい制度です。
ただし、自立支援医療が利用できるのは医師が継続した治療が必要と判断した場合です。したがって、利用したい場合はまずは主治医に相談してみましょう。