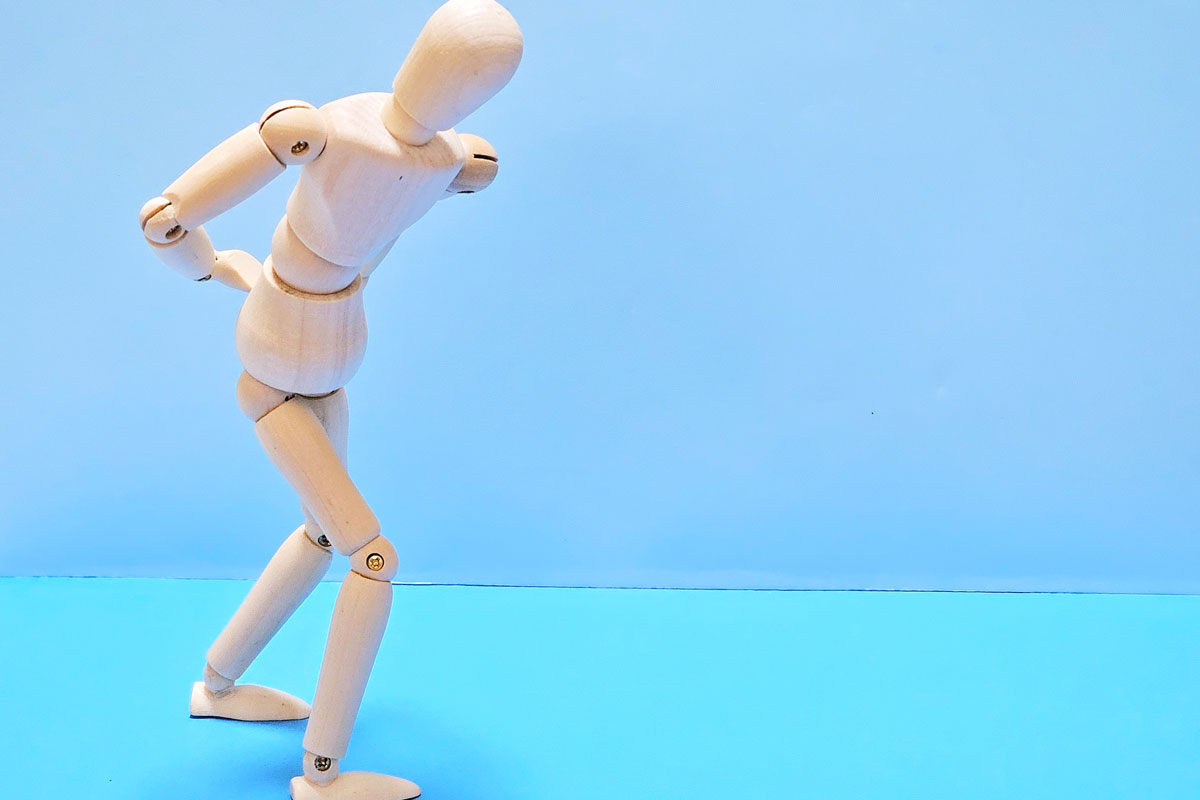更新日:
高齢者の体が傾いてしまう原因と姿勢が崩れることで生じる問題を詳しく解説
高齢者の体が傾いてしまう原因はなんでしょうか。また傾くとどんな問題点があるのでしょう。年齢を重ねれば筋力も落ちて体が傾くことはあたり前といって、崩れた姿勢を改善しないとたくさん問題が表出してきます。
その1つに、転倒しやすくなることを上げることができ、実は「転倒」は、寝たきりになるきっかけを作ってしまいます。そのため、一番避けたいことです。
本記事では、体が傾く原因とそれによって起こる障害を解説し、体の傾きを予防できるトレーニングを解説していきます。
高齢者の体が傾く原因
高齢になると体力が低下したり、病気などの後遺症により椅子に座る姿勢をキープできなくなります。このように座る姿勢をキープできずに、バランスを崩してしまう状態を「座位耐久性が低下している」といいます。座位耐久性の低下は以下の4つが原因と言われています。
- 体力・筋力の低下
- 骨・関節の歪みや拘縮
- 筋肉のこわばりや萎縮
- 視力や聴力の低下
それぞれ紹介していきます。
体力・筋力の低下
ほとんどの人は、立っているよりも、座っていることの方が楽です。しかし、思いのほか座っている姿勢を保つには、体力や筋力を使います。そのため、ある程度体力や筋力がないと座位姿勢を保持するのは困難になるでしょう。
体力や筋力が低下している高齢者にとっては、座ることは疲れる要因になります。そして疲労から、姿勢を保持しにくくなり、前屈みや左右に傾く原因になってしまいます。
骨・関節の歪みや拘縮
高齢者の多くは加齢に伴い、背骨が丸まって真っすぐ伸びなかったり、関節が動きにくくなってきます。同じ状態が長く続くと固まってきてしまい、最終的には拘縮してしまいます。
体の傾きを改善しないと、筋力低下だけでなく、体の内部の骨や関節にも悪影響を及ぼします。身体全体の動きが徐々に悪くなり、左右のバランスを保ちにくくなってしまうのです。
筋肉のこわばりや萎縮
骨や関節だけではなく、筋肉も加齢に伴って、こわばりや萎縮をしてきます。たとえば、足の筋肉がこわばり、萎縮すると踏ん張りが効かなくなります。
座位姿勢を取ろうとしても踏ん張りが効かないと、左右に姿勢が崩れてしまうのは想像できるでしょう。立ち上がり動作なども緩慢になり、日常生活に支障をきたしてしまいます。
座位姿勢だけではなく、立っている姿勢も不安定になるため、転倒のリスクが高くなるでしょう。
視力や聴力の低下
視力や聴力が低下することにより、バランス感覚に影響を及ぼすこともあります。これは、加齢だけの問題ではありませんが、たとえば突発性の難聴やメニエール病などは、耳にあるバランスを司る器官に支障をきたし、バランス感覚が崩れてしまう病気です。
加齢に伴う視力や聴力の低下は、仕方ありません。しかしながら、視力や聴力が低下してもバランス感覚が悪くなることを忘れてはいけません。
体が傾くことの影響
体が傾き続けると身体的にも精神的にも様々な影響をもたらします。
- 食べ物や飲み物が飲み込みにくくなる。
- 床ずれができやすくなる。
- 傾いた状態で骨や関節が固くなる。
- ネガティブな感情になりやすい。
- 椅子などからの転落のリスクが増える。
- 動きにくくなり、動作や運動能力が低下する。
など、様々な問題が生じるでしょう。
この中でも、「飲み込みにくくなる」や「傾いた状態で関節が固くなる」は誤嚥や転倒につながります。さらに、呼吸がしづらくなって息苦しさを常に感じてしまうでしょう。
転倒
体が傾くことの影響として考えられるのは、転倒しやすくなってしまうことです。左右に傾き、さらに体がその姿勢で固定してしまえば転倒しやすくなります。
また、腰が曲がる、円背(えんぱい)になれば、足を上げる動作がやりにくくなり、段差につまづきやすくなってしまいます。転倒の要因は、筋力低下やバランス感覚の低下、聴覚感覚低下などたくさん考えられますが、体の傾きを予防することも大切なことの1つです。
息苦しさ
体が傾くことで起きる影響は、外見だけの問題ではありません。体の内部にも悪影響を及ぼします。たとえば円背は、胸や肋骨が丸まった状態で固まります。
背骨を反らす力が弱くなることで、肺などの内臓、器官が圧迫され続けます。そうなると、呼吸が苦しくなり、常に息苦しい状態になってしまいます。当然、体内の酸素が少ない状態となるため、筋肉の動きは悪くなるでしょう。
誤嚥
誤嚥は食べ物や唾液が胃の方へ行かずに、気管の方へ誤って行ってしまうことです。円背の高齢者は、前を見るために顔を上げる必要があります。自然と顎が上がるので、その時に自然と気道が広がってしまうのです。
食べ物や唾液が気管に入りやすい状態になるので、誤嚥の危険性が高まってしまいます。誤嚥すると咳き込んだり、かなりつらいです。咳き込む力が衰えていると、そのまま肺に食べ物などが入ってしまうため、誤嚥性肺炎などの病気につながります。
座位耐久性を改善するトレーニング
トレーニング中は転倒を防ぐためにも、介助者がしっかり支えて無理のない範囲で行いましょう。これらのことをふまえて、3つほど紹介します。
1つ目は、片足立ちになります。
介助者の補助ありきで、片足立ちのバランストレーニングを行います。5〜10秒を目安に片足立ちしている足を替えましょう。手すりや介助者の手を掴みながら無理のない範囲で行います。
2つ目は、腰回しになります。
時計回り、反時計回りに腰を回すことで、骨盤や股関節のバランスを鍛えることができます。
3つ目は、タンデム歩行になります。
タンデム歩行とは、床に書いてある直線を目印にして、踵とつま先が直線からはみ出ないように歩行する訓練です。バランス力を鍛えることができます。
トレーニングの注意点
バランス感覚と筋力の向上を目的にしたトレーニングです。そのため、ほかのトレーニングに比べると、トレーニングの内容が転倒のリスクが高いものになっています。まずは、無理しないことが大切です。
その上で、介助者がいないときに自主トレをしないことや、すぐに休めるように椅子や車椅子を近くに置いてトレーニングをしましょう。
また、トレーニングに慣れていないのに、回数を増やすことや時間を伸ばすことをしてはいけません。介助者の方々の意見を聞きながら慎重にトレーニングをしましょう。
日々の生活で改善する方法
座位耐久性(座っている時のバランス感覚)は、日々正しい姿勢を保とうとする意識で向上することができます。
- 耳・肩・股関節・膝が横から見たら一直線になるように正しい姿勢で立つ。
- 耳・肩・股関節が横から見たら、一直線になるように正しい姿勢で座る。
- 背筋を伸ばし、踵から入り足全体に体重を乗せて自然と地面と離れるように歩く。
- 骨粗しょう症にならないように、食生活を改善する。
- 良い姿勢を保つために、サポーターなどの器具に頼る。
いきなり、生活の中で取り入れることは難しいかもしれませんが、たとえば正しい姿勢で座ることを意識するだけでも、バランス感覚は向上していきます。くわえて、リハビリなどの専門家と一緒にトレーニングできれば徐々に改善していくでしょう。
まとめ
加齢に伴い、姿勢を保つことができずに傾いてしまうことがあります。そのまま、姿勢で生活していると、転倒のリスクが高まったり、肺が圧迫されて呼吸がしづらくなったりと日常生活に支障をきたす原因になります。
座った時の姿勢やバランス感覚を向上させるために、様々なトレーニングを行うことや正しく姿勢を保つ意識があれば、体の傾きを抑制できます。健康寿命を伸ばすためにも、今日から実践していきましょう。