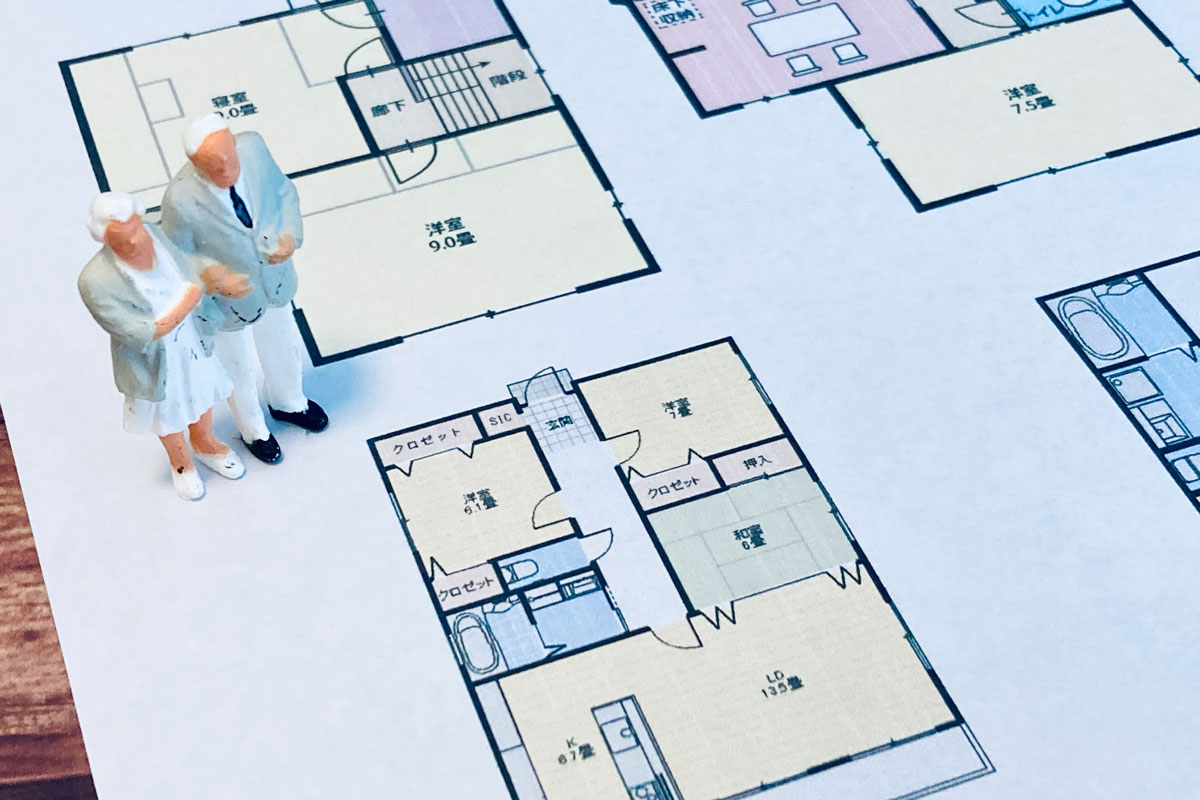更新日:
介護関連の補助金・制度を9つ紹介
ご家族に高齢者がいても、介護が必要ない場合は、介護保険の仕組みや費用を助成する制度について詳しく知らない方も多いでしょう。
しかし、思わぬ病気や怪我をきっかけに、急に介護が必要になることもあります。いざという時に慌てないためにも、事前に利用できる制度を知っておくことが大切です。
本記事では、介護に関連する補助金や制度を紹介します。すでに介護をしている方はもちろん、これからに備えておきたい方もぜひ参考にしてください。
介護関連の主な補助金・制度
日本ではさまざまな補助金や制度を用意しています。ここでは、介護関連の保険や給付金を紹介します。
具体的には以下のとおりです。
- 介護保険
- 福祉用具貸与(レンタル)
- 特定福祉用具販売(購入)
- 居宅介護住宅改修費制度
- 家族介護慰労金
- 介護休業給付金
- 高額療養費制度
- 高額介護合算療養費制度
- 高額介護サービス費制度
ぜひ参考にしてみてください。
介護保険
介護保険は、介護が必要な方を支えるための社会保険制度です。
具体的には、自宅での生活をサポートする「居宅サービス」のほか、施設入所を希望する方のための「施設サービス」があります。
40歳以上の方が加入し、介護が必要になった場合には、必要な手続きを行うことで、上記のサービスを1割~3割の自己負担で利用できる仕組みです。
ただし、介護サービスを利用する方の状態(要介護度)に応じて、介護保険の支給額には上限が定められています。具体的な1ヶ月あたりの支給限度額は、以下のとおりです。
【1ヶ月あたりの支給限度額】
| 要支援1 | 50,320円 |
|---|---|
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担額となる点に注意が必要です。
また、施設利用時に必要となる居住費(滞在費)や食費など、一部の費用は介護保険の支給対象外であり、原則自己負担となります。サービスの利用を開始する際は、事前にケアマネジャーやサービス事業者に費用を確認するようにしましょう。
なお、具体的なサービスの内容や利用条件については、以下の記事をご参照ください。
福祉用具貸与(レンタル)
福祉用具貸与(レンタル)は、車椅子や介護ベッドなどの福祉用具を1~3割の自己負担でレンタルできる制度です。
具体的には、以下の13品目が挙げられます。
- 特殊寝台(介護用ベッド)
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事が不要のもの)
- スロープ(工事が不要のもの)
- 車椅子
- 車椅子付属品
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 徘徊感知機器
- 自動排泄処理装置
自費で購入するよりも費用負担を抑えることができ、メンテナンスもしてもらえるのがメリットです。
一方で、ご利用者の状態(要介護度)によって、レンタル対象となる品目は異なります。レンタルを希望する場合は、福祉用具専門員やケアマネジャーに相談してみると良いでしょう。
具体的な利用条件やレンタルまでの流れについては、以下の記事にて詳しく解説しています。
福祉用具購入費制度
福祉用具購入費制度は、介護保険の要介護(要支援)認定を受けた方が、福祉用具を購入する際に、費用の一部が助成される制度です。
介護保険で購入できる福祉用具は以下のとおりです。
- 腰掛便座(ポータブルトイレ)
- 排泄予測支援機器
- 自動排泄処理装置の交換部品
- 入浴補助用具(入浴用椅子や手すり)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
さらに、2024年の制度改正により、以下の福祉用具はレンタル・購入のいずれかを選択できるようになりました。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点つえ(松葉づえを除く)
- 多点つえ
福祉用具購入費の利用限度額は1年間につき10万円までで、購入費用のうち1~3割が自己負担となります。
ただし、ホームセンターやインターネットで購入した場合は、福祉用具購入費制度は利用できません。介護保険を適用するには、都道府県の指定を受けた事業所から購入する必要があることを知っておきましょう。
居宅介護住宅改修費制度
居宅介護住宅改修費制度とは、介護が必要な方が自宅で安全に暮らせるよう、住宅改修の費用を介護保険で助成する制度です。
支給対象となる主な改修内容は以下のとおりです。
- 廊下や階段、トイレなどの手すり設置
- 段差の解消
- すべり止めの設置や床材の変更
- 開き戸から引き戸など扉の取り替え
- 和式から洋式への便器の取り替え
支給限度額は介護度に関わらず、利用者1人につき20万円です。1回の改修で使い切らず、数回に分けて利用することも可能です。
ただし、引っ越しや介護度の大幅な上昇など特別な事情がない限り、原則として再給付は受けられないため、計画的に活用しましょう。
家族介護慰労金
家族介護慰労金とは、重度の介護が必要な方を在宅で介護支援する家族に年間10~12万円程度の慰労金を給付する制度です。
おもな条件は以下のとおりです。
- 介護保険の認定区分が要介護4以上である
- 過去1年間に介護保険のサービスを利用していない
- 1年以上同じ市町村で生活していること(長期入院をしていない)
- 市民税非課税世帯である
家族介護慰労金は市区町村ごとに実施状況や支給条件が異なります。ご家族を自宅で介護している方は、確認してみましょう。
介護休業給付金
介護休業給付金は雇用保険の被保険者が、配偶者や親、子などを介護するために長期休業を取得した際に、賃金のおよそ67%が支給される制度です。
介護が必要な方1人につき、93日を限度に3回まで分割して取得できます。介護休業給付金のおもな申請条件は以下のとおりです。
- 介護の対象となる家族が、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある
- 被保険者が、休業期間を明示して事業主に申し出たうえで休業している
同居していない家族を介護する場合も対象となる一方、雇用形態や給料の支払い状況によって支給金額や申請可否が異なる場合もあります。詳しくは勤務先やハローワークにご相談ください。
高額療養費制度
高額療養費制度は、医療費の自己負担額が高額になった場合に、上限額を超えた分を払い戻す制度です。急な入院や手術だけでなく、通院や薬代が重なったときにも利用できます。
月ごとの上限額は年齢と世帯の収入によって異なります。以下に、69歳以下と70歳以上のそれぞれの上限額をまとめました。
【69歳以下の高額療養制度の上限額】
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
|---|---|
| オ 住民税非課税者 |
35,400円 |
| エ ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
| ウ 年収約370~約770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| イ 年収約770~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
| ア 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
【70歳以上の高額療養制度の上限額】
| 適用区分 | 外来(個人ごと) | ひと月の上限額 |
|---|---|---|
| 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
8,000円 | 15,000円 |
| 年収156万~約370万円 月収26万円以下/課税所得145万円未満 |
18,000円 | 57,600円 |
| 年収約370万~約770万円 標報28万円以上/課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 年収約770万~約1,160万円 月収53万円以上/課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
| 年収約1,160万円~ 月収83万円以上/課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
同じ世帯で1年のうちに3回以上、上限額を超えた場合は「多数該当」となり、4回目以降の自己負担上限額はさらに引き下げられます。
なお、負担上限額に含まれるのは医療保険の自己負担分のみで、自費診療や差額ベッド代は対象外となるため注意しましょう。
高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、1年間の合計が上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。医療・介護それぞれにかかる費用が大きくなりやすい高齢世帯の費用負担を軽減することを目的としています。
対象者の区分と上限額は以下のとおりです。
| 70歳未満 (介護保険+被用者保険または国民健康保険) |
70〜74歳未満 (介護保険+被用者保険または国民健康保険) |
75歳以上 (介護保険+後期高齢者医療) |
|
|---|---|---|---|
| 市町村民税世帯非課税 (年金収入80万円以下等) |
34万円 | 19万円 (介護サービスの利用者が複数いる場合は31万円) |
19万円 (介護サービスの利用者が複数いる場合は31万円) |
| 市町村民税世帯非課税等 | 34万円 | 31万円 | 31万円 |
| ~年収約370万円 | 60万円 | 56万円 | 56万円 |
| 年収約370~約770万円 | 67万円 | 67万円 | 67万円 |
| 年収約770~約1,160万円 | 141万円 | 141万円 | 141万円 |
| 年収約1,160万円~ | 212万円 | 212万円 | 212万円 |
毎年8月から翌年7月までの1年間単位で自己負担額を計算し、上限額を超えた場合は、申請により払い戻しを受けられます。具体的な手続きの方法については、お住まいの自治体へお問い合わせください。
高額介護サービス費制度
高額介護サービス費制度は、デイサービスや福祉用具貸与(レンタル)など、介護保険上のサービスを利用した際の費用負担を軽減するための制度です。
介護度ごとの支給限度額とは別に、世帯の収入に応じて月ごとの負担上限額が設けられており、上限を超えた場合は差額が支給されます。
高額介護サービス費制度の負担上限額は以下のとおりです。
| 区分 | 負担上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380~690万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 市町村民税課税~課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 市町村民税非課税(世帯全員) | 24,600円(世帯) |
| 前年の収入80万円以下など | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護受給世帯など | 15,000円(世帯) |
参考:令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます
なお、事前に申請しておくことで、毎月手続きなしで自動で払い戻しを受けることが可能です。具体的な手続きの方法についてはケアマネジャーや自治体にご確認ください。
まとめ
介護保険を利用すれば、介護サービスの利用料を軽減できますが、多くの介護が必要な方や、医療が必要な方にとっては、それだけでは不十分な場合もあります。
介護費用を助成する制度は複数用意されているものの、多くは申請しなければ受給できません。
この記事を参考に、活用できる制度を正しく理解し、将来に備えておきましょう。
介護について相談できる窓口を知っているだけでも、いざという時の安心につながります。福祉用具や自宅での介護については、ぜひヤマシタへご相談ください。