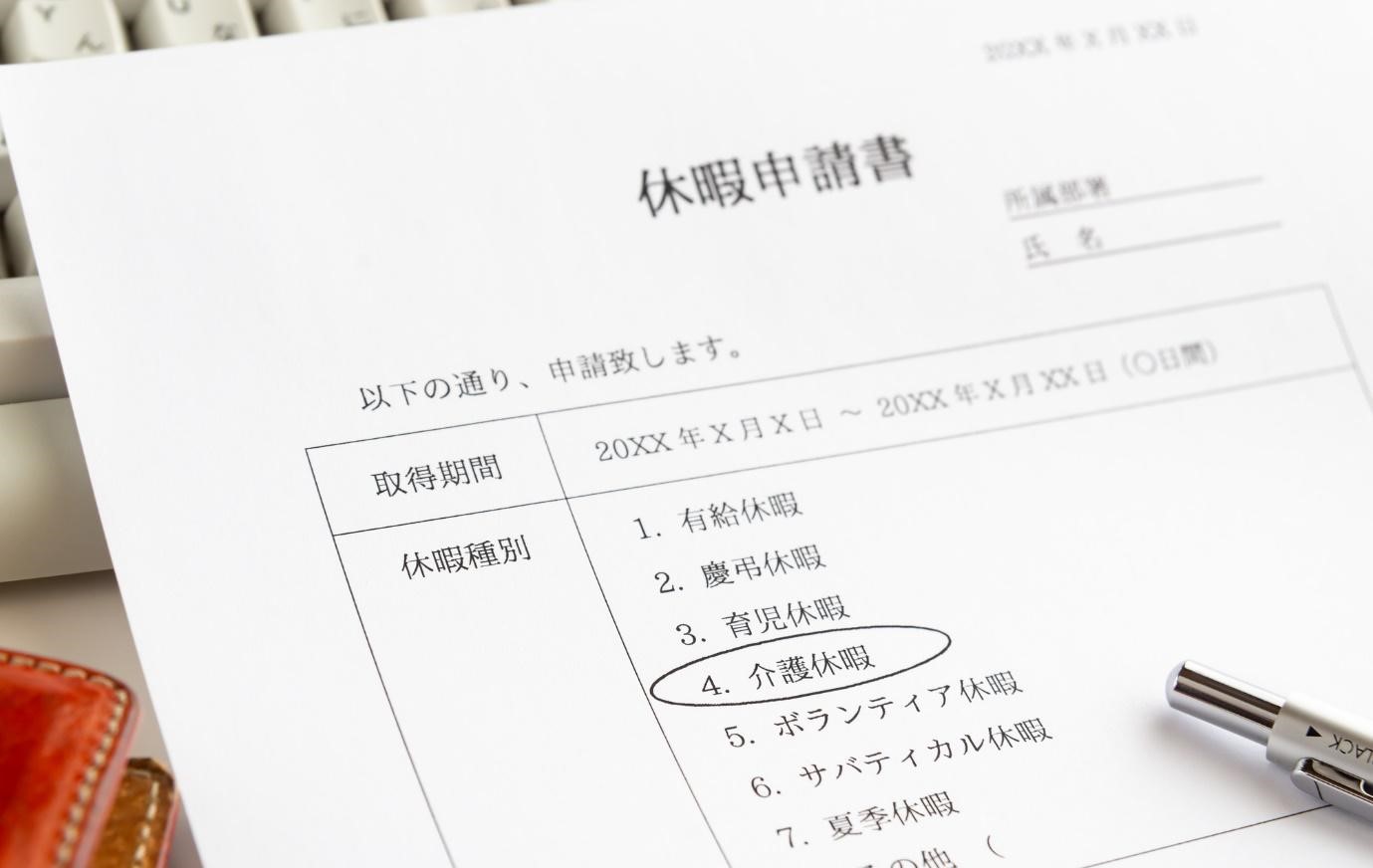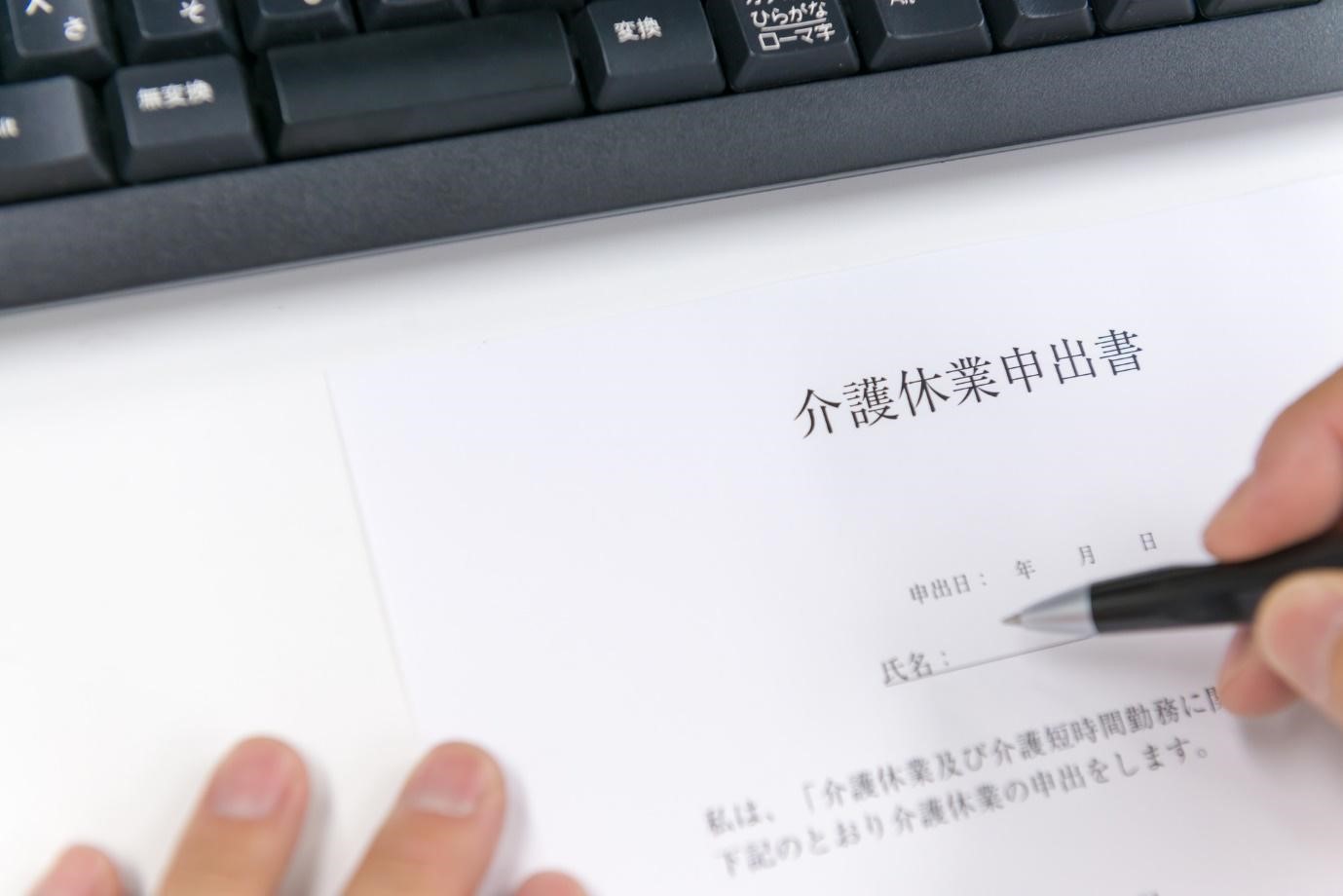更新日:
介護休業制度とは?介護休暇制度との違いや給付金制度を解説
介護休業と介護休暇は、家族の介護が必要になった際に「仕事を休まざるを得ない」「仕事を辞めないといけない」といった状況を改善するために設けられた制度です。
2021年1月1日から、介護休暇の適応範囲が緩和され、以前よりも取得しやすくなりました。
介護は突然必要になることが多いため、万が一に備えて知っておきたい制度の一つといえるでしょう。
この記事では、介護休業と介護休暇の違いや給付金について紹介します。
介護休暇とは?
介護休暇とは、家族の介護が必要になった場合に、仕事を辞めることなく仕事と介護を両立するための制度です。
超高齢社会の日本では、介護のために仕事を辞めざるをえない「介護離職」が社会問題となっており、その対策の1つとして介護休暇が設けられました。
介護休暇は、労働者の家族がけがや病気により、2週間以上の世話や介護が必要な状態(要介護状態)になった場合に取得できる休暇制度です。
介護休暇は会社の規模にかかわらず取得可能で、会社に規定がない場合でも要件を満たしていれば、手続きをおこなえば取得できます。
取得できる日数は、以下のとおりです。
| 対象者 | 取得できる日数(年間 ) |
|---|---|
| 1人 | 5日 |
| 2人以上 | 10日 |
※毎年4月1日~翌年3月31日の1年間
介護休暇は、時間単位で取得も可能ですが、労使協定により1日単位でしか取得できない企業もあります。
労働時間の短縮制度もある
介護休暇に加え、介護と仕事を両立するための手段として、労働時間を短縮できる制度も設けられています。取得要件は介護休暇と同様に、要介護状態の家族がいる場合に利用可能です。
短時間勤務には次のような種類があります。
- 1日あたりの勤務時間を短くする
- 週または月の所定労働時間を短くする
- 週または月の所定労働日数を短くする
- 労働者が勤務しない日程や時間を請求できる
上記のような勤務方法のほか、次のような制度を導入して、介護休暇の要件を満たす会社もあります。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| フレックスタイム制度 | ●労働時間を1日単位ではなく月単位で管理するシステム●あらかじめ設定された月の労働時間はあるが、1日の勤務時間などは自分で設定できる●始業や終業時間も自分で決められる |
| 時差出勤の制度 | ●始業や終業時間を早めたり遅くしたりできるシステム ●通勤ラッシュを回避できるなどの特徴がある |
| 介護費用の助成措置 | ●労働者が利用する介護サービスの費用を助成する制度 |
ただし、次の人は時間短縮制度の対象外です。
- 入社1年未満
- 1週間の所定労働日数が2日以下
介護休業と介護休暇の違い
家族の介護が必要になった場合に取得できる制度には、介護休暇のほかに「介護休業制度」があります。介護休業と介護休暇の違いは、次の表のとおりです。
| 介護休業 | 介護休暇 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 取得単位 | 家族の介護のために長期的な休暇が取れる |
| 取得できる単位数 | 数週間から数カ月 | 1日、または時間単位 |
| 取得可能日数 | 家族1人につき、年間通算93日 ※分割取得可能・最大3回まで |
家族1人につき、年5日まで ※2人以上の場合は、年10日まで |
| 給付金の有無 | 介護休業給付金の支給あり | なし |
介護休業は、数週間から数カ月間の長期休暇が取得できる制度で、年間通算93日まで取得可能です。
この期間を最大3回に分けて利用することが可能となっており、例えば1カ月ごとに3回取得する場合や、1回目は20日間、2回目は73日間の2回に分けて取得する場合など、必要に応じて柔軟に使用できます。
一方、介護休暇は、1日または時間単位で取得できるため、要介護者のデイサービスの準備や通院・施設手続きなどで利用できるでしょう。
関連記事:介護保険の申請手続きの流れ|窓口・条件・必要書類を解説
介護休暇と介護休業の法的解釈
介護休暇や介護休業は1995年に始まり、数回の改正がおこなわれ現在の制度となりました。これまでの経過と変更点は以下のとおりです。
| 年 | 改定内容 |
|---|---|
| 1995年4月1日から | ●育児休業法が「育児・介護休業法」に改正される ●介護休業法が法制化する |
| 1999年4月1日から | ●介護休業制度が義務化する |
| 2010年7月1日から | ●介護休暇制度が施行される |
| 2017年1月1日から | ●介護休業の最大3回まで分割取得が可能になる ●介護休業とは別に利用開始から3年の間に2回以上、所定労働時間短縮措置を講じる ●介護の必要性がなくなるまで残業が免除可能になる |
| 2021年1月1日から | ●原則すべての労働者が対象となる ●時間単位での介護休暇が取得可能になる |
| 2022年1月1日より | ●労働条件・対象者が拡大する |
2025年には法改正され、介護休暇を取得できる労働条件がさらに緩和される予定です。また、介護離職を防ぐために、早い段階からの情報周知や個別の周知・意向確認も義務付けられます。
介護休暇や介護休業に関して、事業主は拒否できません。また、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」では、休暇取得にともなう解雇や減給はできないとされています。
つまり、労働者は法により、介護休暇が取得できる権利があるということです。
しかし、仕事を続けながら介護を両立させる目的で活用する制度のため、会社に対して強引な要請は控えたいものです。
できるだけ、前もって上司などと相談し、円滑に取得できる環境を作っておくと良いでしょう。
介護休暇の対象者と手続き方法
介護休暇を取得するには、いくつかの要件があります。
ここからは、介護休暇取得の対象者や手続きについて確認していきましょう。
家族に介護対象者がいる労働者
2021年1月1日から介護休暇を取得できる労働者条件が緩和されました。内容は以下のとおりです。
| 2020年12月31日まで | 2021年1月1日以降 | |
|---|---|---|
| 労働者条件 | 1日の所得労働時間が4時間以下は対象外 | 原則すべての労働者を対象 |
| 取得できる単位数 | 1日または半日単位で取得 | 1日もしくは時間単位で取得 |
対象範囲が拡大されたことで、すべての労働者が対象になりました。労働条件の変更にあわせて取得できる単位にも変更があります。
ただし、労使協定を締結している場合、次の方は取得要件から外れます。
- 入社6カ月未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
2025年4月1日の法改正では、「入社6カ月未満の労働者」の対象外となる要件は廃止されます。※2024年11月時点
対象となる家族の範囲
介護休暇を取得するためには「要介護状態の家族がいること」が要件です。
要介護状態になった家族の対象範囲は次のとおりです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 実の父親・母親
- 配偶者の父親・母親
- 子ども(養子含む)
- 祖父・祖母(配偶者の祖父母は除く)
- 兄弟・姉妹
- 孫
上記以外の家族は含まれないため注意が必要です。
手続きの流れ
介護休暇を取得する場合、書面や口頭によって申請します。介護休暇は突然必要になる場合もあるため、休暇当日に申請も可能です。
基本的には、企業や会社内の規定(就業規則)に従って申請をおこないます。そのためにも、事前に必要な書類や手続きについて確認しておきましょう。
また、介護休暇が必要になると事前にわかっている状況なら、上司や同僚などに前もって相談しておくと、取得の際にも理解を得られやすくなるでしょう。
会社に申請書類がない場合は、厚生労働省から様式例が公開されていますので、活用してください。
介護休業の対象者と手続き方法
介護休業と介護休暇は、対象者や申請する方法などに違いがあります。
ここからは介護休業の対象者や申請する手続きの方法について確認していきましょう。
特定の条件を満たす労働者
介護休暇と比べ、介護休業は長期で休暇を取得するため、対象となる労働者の条件が異なります。2022年4月1日から取得条件の改正があったため、あわせて確認していきましょう。
| 2022年3月31日まで | 2022年4月1日以降 | |
|---|---|---|
| 労働者条件 | 介護休暇取得予定日から93日+6カ月経過する日までに雇用契約が更新される者 | |
| 取得条件 | ●介護休暇の取得予定日から93日以内に雇用契約が切れる人は対象外 ●入社1年目は対象外 |
●介護休暇の取得予定日から93日以内に雇用契約が切れる人は対象外 |
改正によって、過去に取得要件としてあった「入社1年目は対象外」がなくなりました。
ただし、労務協定を提携している場合、次の方は介護休業の取得要件から外れるため注意しましょう。
- 入社1年目の方
- 申出の日から93日以内に雇用期間が終了する方
- 1週間の所定労働日数が2日以下の方
対象となる家族の範囲
介護休業の対象になる家族の範囲は、介護休暇と同様に「要介護状態の家族がいること」が要件です。
要介護状態になった家族の対象範囲は次のとおりです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 実の父親・母親
- 配偶者の父親・母親
- 子ども(養子含む)
- 祖父・祖母(配偶者の祖父母は除く)
- 兄弟・姉妹
- 孫
上記以外の家族は含まれないため注意が必要です。
手続きの流れ
介護休暇と異なり、介護休業を取得する場合は、会社に対して2週間前までに書面での申請が必要です。
また、1回の休業に対して一度だけ、理由を問わず介護休業の終了予定日を延ばせます。ただし、この場合も休業終了予定日の2週間前までに延長の申し出が必要です。
制度として利用できる権利である一方、会社復帰をスムーズにおこなうためには、申請前に会社とよく話し合いをしておきましょう。
会社に書類が用意されていない場合は、厚生労働省から様式例が公開されていますので、活用してください。
介護休暇と介護休業の選び方
介護休暇と介護休業は、どちらも仕事と介護を両立するための制度ですが、それぞれ異なる特徴があります。
「介護休暇」では短期的な休みを活用できる
介護休暇は、短期間の休暇が必要な場合に適した制度です。
例えば、通院の付き添いや介護サービスの手続きなどに活用できます。
要介護状態の家族が、一時的に支援が必要な状態であれば、介護休暇取得を優先すると良いでしょう。
「介護休業」では仕事との両立を目指せる
介護休暇は、継続的に介護が必要な場合に利用しましょう。
例えば、介護サービスの利用を検討する場合や入所施設を探す、利用できる介護サービスの検討・契約などです。
介護保険サービスを利用する際は、本人の面談や健康診断書などの作成・契約が必要な場合が多く、利用開始までに時間を要するケースも珍しくありません。
また、状況によっては家の改修工事が必要になることも考えられます。その場合は、介護保険を利用して住宅改修をおこなうことが可能です。
介護休業を取得する際は、将来的に仕事との両立することを視野に入れ、継続的に介護ができる環境を作りましょう。
ヤマシタでは住宅改修の申請代理から工事まで、専門スタッフが対応しております。
介護のことでお困りでしたらお気軽にご相談ください。
営業所は安心の365日体制。
お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。
メールは365日24時間受付
受付時間 9:00~18:00
介護休業給付金制度を活用できる
介護休業は休暇を取得できるだけではなく、その期間の介護休業給付金を受け取れます。家族の介護に加えて、収入の負担や不安があるなど「仕事を休めない方のため」にある支援制度です。
介護休業給付金制度の取得には、要件があり、申請も必要となるため確認していきましょう。
給与の一部を受給できる制度
介護休業給付金制度を利用すると、休業中に給付金を受給できます。受給の要件は以下のとおりです。
- 雇用保険の被保険者
- 職場復帰を前提とした介護休業
- 介護休暇取得日からさかのぼって2年間の間に11日以上勤務した月が12カ月以上
- 介護休業中に仕事をした日数が10日以下
- 介護休業中に発生する賃金が、休業前の80%未満
これらの要件を満たしていれば、最大67%の給付が受けられます。
介護休業中に受け取れる給与を含めた給付は、休業前の給与額に対して最大80%までです。
例えば、休業中に給与が50%支払われていた場合は、給付額は「80%-50%=30%」となり、介護休業給付金として30%支給されます。
元の給与額から介護休業給付金が支給される目安は以下のとおりです。
| 元の給与の月平均額 | 介護休業給付金の目安 |
|---|---|
| 15万円 | 10.1万円 |
| 20万円 | 13.4万円 |
| 25万円 | 16.8万円 |
| 30万円 | 20.1万円 |
| 35万円 | 23.5万円 |
※計算方法は、休業開始時の給与(日額)×支給日数×67%
給付金を受け取るには、管轄のハローワークに申請書の提出が必要です。
以下のサイトからハローワークの場所を探せます。
参考:厚生労働省「全国ハローワークの所在案内」
また、申請用紙や詳しい手順については下記をご参照ください。
参考:厚生労働省「介護休業給付の内容及び支給申請手続きについて」
ほかの給付金とは一緒に利用できない
介護休業給付金制度は、「産前産後休業」「育児休業」といったほかの給付金制度との併用ができません。
別の休業制度を利用すると、それ以前に取得していた休業制度が上書きされてしまうため注意が必要です。
育児と介護が重なった場合などは、それぞれの休業制度から、どちらを選択するかを検討しましょう。
まとめ
介護休暇と介護休業はどちらも仕事と介護を両立させるための支援制度ですが、状況や目的によって使い分けます。
介護休業は、まとまった期間の休暇を取得できるため、在宅の状況や介護サービスを整える時間に充てられます。
要介護者の身体状況にあわせて、福祉用具の介入や住宅の改修も必要になるかもしれません。
家族が要介護状態になったときは、無理せずに介護休暇や介護休業制度を利用して、介護の環境を整えましょう。
福祉用具のレンタルや住宅改修など、介護のことでお悩みの際は、お気軽にヤマシタまでご相談ください。
営業所は安心の365日体制。
お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。
メールは365日24時間受付
受付時間 9:00~18:00