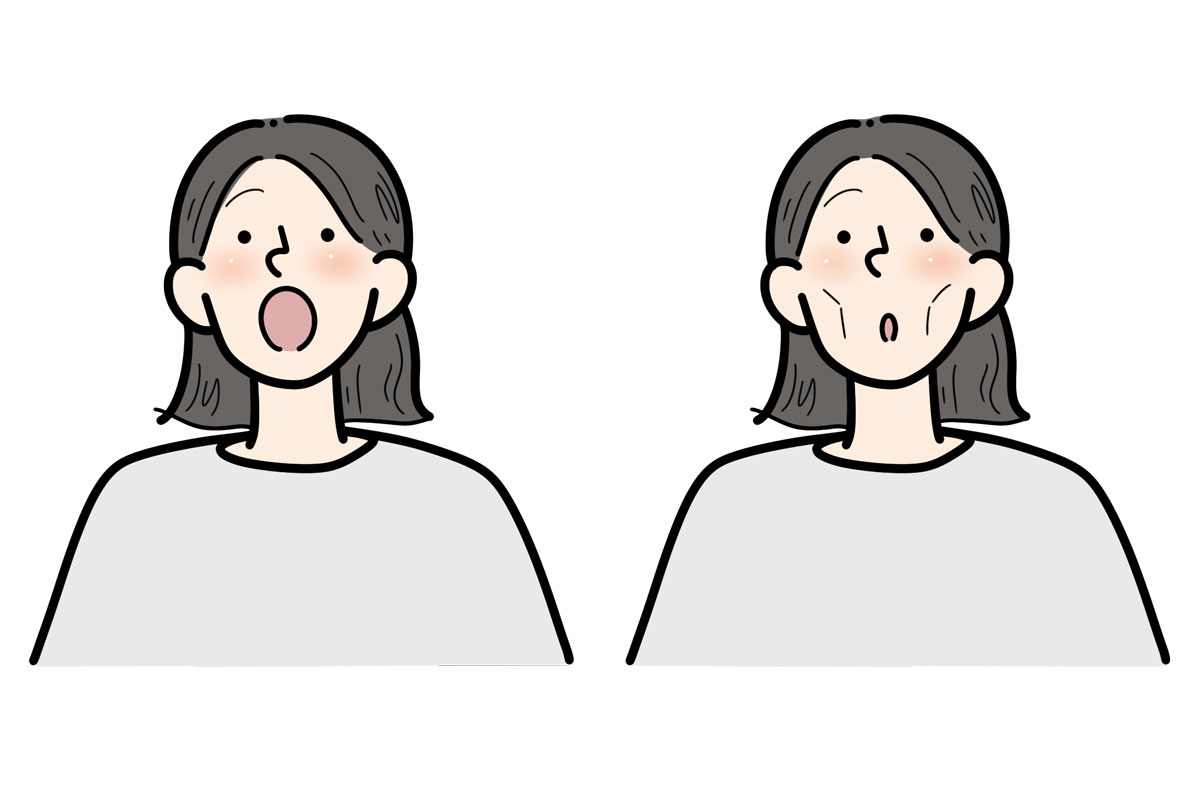更新日:
誤嚥(ごえん)とは?予防策や対処法をわかりやすく解説
高齢者の方に食事介助をしていると、高頻度でむせてせき込むことがあります。
食事中のむせ込みやせき込みは「誤嚥」(ごえん)と呼ばれ、どの世代の人にも起こる現象です。
しかし、食べ物を飲み込む力が弱くなってきた高齢の方は、特に誤嚥が増えてきます。
たかが誤嚥と甘く考えるのは危険です。
高齢者の誤嚥は肺炎の原因ともなり、場合によっては命にかかわるケースも多くみられます。
この記事では高齢の方に誤嚥が多い理由や誤嚥を防ぐ方法、実際に誤嚥が起きてしまった場合の対処方法を詳しく解説します。
誤嚥とは
誤嚥とは、食事を飲み込む際に、食べ物や水分が誤って気管に入ってしまうことをいいます。
誤嚥で激しくせき込んでしまうのは、気管に入ってしまった食べ物や飲み物を吐き出そうとする体の正常な反応です。
誤嚥そのものはどの年代にもあることで、誰しも一度は経験したことがあるはずです。
しかし高齢者にとっての誤嚥は、若い世代とは大きく意味合いが異なります。
高齢になると、飲み込む力が弱くなることで誤嚥しやすくなります。
さらに誤嚥してしまった食べ物や飲み物を吐き出そうとする反射の力も弱くなります。
そのため誤嚥をした食べ物や飲み物に付着する細菌が、気管や肺で増殖し、誤嚥性肺炎を招いてしまうケースも多くあります。
食事中だけではなく、睡眠中にも気づかないうちにだ液を誤嚥していることもあります。
誤嚥が起こる原因
誤嚥は飲み込む力(嚥下力)の低下によって起こります。
食べ物を飲み込む際には、嚥下反射という生体反射が起こります。
嚥下反射とは食べ物を飲み込む際に、のどの奥にある「喉頭蓋」と呼ばれる器官が閉じて気道の入り口をふさぎ、食べ物が気管に入ることを防ぐ反射です。
高齢になると嚥下反射が低下するため、食べ物を飲み込む際に喉頭蓋が閉じにくくなってしまいます。
そのため食べ物や飲み物が気管に入りやすくなり、誤嚥しやすい状態になってしまいます。
誤嚥が起こりやすいタイミング
誤嚥は飲み込もうとするタイミングだけで起こるわけではなく、思いがけないタイミングでも起こり得ます。
ここでは、誤嚥が起こりやすいタイミングとして、食事中と睡眠中について説明します。
食事中
誤嚥は食事中に多く起こります。
食べ物を飲み込むタイミングで起こるのはもちろんですが、実は高齢者の誤嚥は食べ物を噛んでいるときや飲み込んだあとにも起きています。
高齢者は噛む力も弱くなるため、口の中に食べ物がある時間は長くなりがちです。
飲み込む力も弱いため、しっかり飲み込んだように見えても、口の中にはまだ食べ物が残っていることもよくあります。
高齢者の誤嚥は、食べ物が口の中にある限り、常に起こり得ます。
少量の誤嚥は、むせ込みやせき込みがみられないことが多く、気づかないうちに肺炎になってしまう怖さがあります。
食事介助の際には一口の量は少なめに、しっかり飲み込める量とすることが大切です。
また食事後は口腔ケアをして、口の中に食べ物を残さないように心がけましょう。
睡眠中
誤嚥は食事中だけでなく、睡眠中にも起こります。
睡眠中はだ液の誤嚥が起こります。
口の中のだ液が睡眠中にのどの奥に流れ込み、少量ずつ誤嚥をしていることがあるのです。
激しくせき込んだりしないケースも多く、気づきにくいタイプの誤嚥です。
口腔内の細菌が、だ液を通じて気管や肺で繁殖することで誤嚥性肺炎を引き起こします。
口腔ケアを丁寧に行い、細菌が繁殖しにくい口腔環境に整えましょう。
また睡眠中には、胃の中の食べ物が逆流して誤嚥をするケースもあります。
睡眠中の逆流による誤嚥を予防するためには、以下のような工夫が効果的です。
- 食後2時間以上経過してから就寝する
- ベッドの上半身側を30度程度上げた状態で就寝する
夜間に不穏(夜間に興奮したり、多動がみられる状態)があり睡眠導入剤などを服用している場合には、睡眠中の嚥下反射が低下しており、誤嚥のリスクがさらに高くなります。
睡眠導入剤を投与されている方は、睡眠中の誤嚥には特に注意を払いましょう。
誤嚥の症状
誤嚥の症状には以下の4点があげられます。
- よくむせ込んで、せき込んでいる
- 痰がからんでいる
- 食事のあとに呼吸をする際、痰がからむようなヒューヒュー音がある
- 食事中にガラガラ声やかすれ声になる
気道に食べ物が入ると声質が変化したり、呼吸の際に異音が聞こえたりすることが増えます。
食事の前後の声や呼吸の音に注意しましょう。
少量の誤嚥の場合には、誤嚥をしていても激しくむせたりせき込んだりしないケースもあります。
「むせ込みがないから誤嚥をしていない」というわけではありません。
日頃から声や呼吸音に注意を払っておきましょう。
誤嚥性肺炎とは
食べ物や飲み物に付着した細菌が、誤嚥によって気管や肺で増殖し、肺炎を引き起こすことを誤嚥性肺炎といいます。
口腔内には細菌が多く存在しており、特に高齢者はだ液の量が少なくなってしまうため、口腔内に細菌が繁殖しやすい傾向です。
食べ物と一緒に口腔内の細菌も多く誤嚥してしまうため、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高くなってしまいます。
誤嚥をさせないことはもちろん、丁寧に口腔ケアを行い口内の細菌の発生を抑えることも、誤嚥性肺炎予防には大切です。
誤嚥性肺炎の症状
誤嚥性肺炎の症状は以下のとおりです。
- 37.5度以上の発熱
- 咳が長く続く
- 呼吸が荒く、息苦しそうに見える
- 黄色や緑色の痰が出てくる
- 寝ていることが多く、いつもより活気がなくだるそうに見える
- 食欲がない
発熱や咳といった症状があればわかりやすいのですが、目に見える症状がなくても誤嚥性肺炎が進行していることもあります。
熱などの症状がなくても「なんとなくいつもと違う」というご家族の感覚は、とても大事です。
いつもと様子が違うと感じたら「様子を見ておこう」「これぐらいで相談するのは申し訳ない」などとは思わずに、いつもと何か違うと感じたら、すぐに主治医に相談しましょう。
身近にいるからこそ気づける体調の変化もあるのです。
誤嚥を予防するには
誤嚥は食事の量や硬さ、姿勢、口腔内のケアを行うことによって予防することができます。
ここからは誤嚥を予防する方法について紹介します。
誤嚥しやすい料理を避ける
さらさらとした水分や、粘度の低い食べ物は誤嚥を引き起こしやすくなります。
誤嚥を予防するためには、水分も食べ物も少しとろみをつけてあげると良いでしょう。
また、高齢になると食べ物を噛む力も弱くなっています。
硬い食べ物は口の中で咀嚼する時間が長くなり、誤嚥しやすくなります。
噛みやすい柔らかさにすることで、誤嚥を予防します。
とはいえ、毎回介護のための食事を用意するのは時間も手間もかかります。
高齢者の食べやすさに配慮したレトルトの介護食もおすすめです。
高齢の方が誤嚥しにくい柔らかさ、粘度に調整されており、温めるだけで介護食が完成します。
一食で必要な栄養素が摂れるよう、高齢者のための栄養バランスも考えられている点も助かります。
介護用品の通販サイト、ヤマシタオンラインストアでもレトルト介護食を扱っています。
ヤマシタオンラインストアでは、主食からおかず、デザートまで幅広い種類の介護食を取り扱っています。
常温での保存が可能な介護食も多く、災害時の備蓄としてもおすすめです。
参考:食事関連,介護食品 | 日本最大級の介護用品・福祉用具総合通販サイト ヤマシタオンラインストア
口腔内を清潔に保つ
誤嚥をすると、食べ物や飲み物と一緒に口腔内の細菌も誤嚥してしまいます。
飲み込んでしまった口腔内の細菌が、気管や肺で繁殖することで、誤嚥性肺炎が誘発されます。
細菌の発生を防ぐため、口腔内の清潔を保ちましょう。
特に、食事の前後に口腔ケアをして、食べかすを残さないことはとても大切です。
口の中に残った水分や食べ物はガーゼや吸引できれいに掃除しておきましょう。
高齢となるとだ液の量も減少します。だ液が減少し口の中が乾燥状態となると、口腔内の細菌が増えてしまいます。
口腔ケアで口に刺激を与えることでだ液の分泌を促し、細菌の繁殖を抑えます。
嚥下機能の向上を図る
嚥下機能を向上させる方法には、嚥下トレーニングがあります。
嚥下トレーニングとは、口やあご、舌など咀嚼につながる筋肉に刺激を与え、動きをスムーズにすることで咀嚼力を向上させるトレーニングです。
舌をベーっと前や左右に突き出したり、口を大きく開けたり、いーっと横に引いたり、きゅっとすぼめたり、口を大きく動かす動きが嚥下機能の向上には効果的です。
口腔ケアは生活の中で行える嚥下トレーニングです。
口腔ケア用の綿棒で舌を押して刺激したり、口の中から頬を上から下に押してマッサージしたりすることは嚥下力の向上にもつながります。
食事中の姿勢に気をつける
食事中の姿勢は誤嚥対策にはとても重要です。
姿勢がねじれていると、あごやのどの筋肉がスムーズに動かず、誤嚥しやすくなってしまいます。
以下では椅子とベッドで食事する際の姿勢について説明します。
椅子で食事をする場合
自分で食事を摂れる方は、椅子に座って姿勢を正し、あごを引いた姿勢で食べましょう。
椅子の高さは、両足がしっかり床につく高さが適切です。
もし両足が床に届かないときには、足台を置くと良いでしょう。
体が左右のどちらかに大きく傾いていたり、猫背になったり、首がのけぞってあごが上を向いてしまう姿勢は避けます。
食べ物を飲み込みにくく、誤嚥しやすくなります。
もしまっすぐに座れない場合やあごが上向きとなる場合には、クッションを利用して、誤嚥しにくい姿勢にサポートしてあげるとよいでしょう。
また介護椅子を利用するのもおすすめです。
ヤマシタでも介護椅子の購入・レンタルについてご相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
営業所は安心の365日体制。
お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。
メールは365日24時間受付
受付時間 9:00~18:00
ベッドで食事をする場合
ベッドで食事をする場合は、上半身を45~60度程度に上げ、膝の下にはクッションを入れて姿勢を安定させます。
食事介助が必要な場合には、ベッドの角度は30度程度に上げるとよいでしょう。
足の裏にも枕やクッションを置くと、より姿勢は安定します。
もし首やあごがのけぞってしまい、あごが上向きになってしまう場合には、頭の下に大きなクッションを入れてあげましょう。
あごを引いた姿勢に整えると、誤嚥を防ぐことができます。
以下のようなリクライニングベッドの使用も非常に便利です。
ポジショニングベッド 3モーター
「ポジショニングベッド」は誤嚥しにくい首の角度に調整し、食事を摂りやすい自然な体の姿勢をサポートする介護用ベッドです。
ほかのベッドと比べ、背中やお腹に負担がかかりにくい姿勢となるので、呼吸がしやすく、誤嚥を防ぎ、疲れにくい快適な姿勢でのお食事が可能です。
| 縦×横×高さ(ボード含む) | 幅100×長さ211×高さ60~102cm |
|---|---|
| 高さ | 60~102cm |
| 背上げ角度 | 0~70度 |
| 膝上げ角度 | 0度~22度 |
| 重量 | 96.9kg |
ベッド横から差し込んで使用する「サイドテーブル」もあわせて使用すると、ベッド上でも安定して食事できます。
サイドテーブル
| サイズ | 本体サイズ:幅44.5×長さ90.7×高さ61~92.5cm 天板サイズ:幅40×長さ90cm |
|---|---|
| 重量 | 14kg |
リクライニングベッド、サイドテーブルはヤマシタでもレンタルを扱っております。お気軽にご相談ください。
営業所は安心の365日体制。
お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。
メールは365日24時間受付
受付時間 9:00~18:00
食後すぐに横にならない
食後にすぐに横になってしまうと、胃から食道に食べたものが逆流し、誤嚥しやすくなってしまいます。
逆流による誤嚥を予防するため、食後は2~3時間程度を目安に、テレビやラジオをつけるなどして座った姿勢のままでいるようにしましょう。
タオルたたみや折り紙など、レクリエーションの時間を設けてもよいでしょう。
タオルたたみや折り紙は介護施設でもよく行われているレクリエーションです。
指先のリハビリにもなり、脳の活性化にもつながります。
誤嚥予防のトレーニング
誤嚥を予防するためには、口腔機能や嚥下機能を維持・向上させるトレーニングが有効です。
ここでは、代表的な「嚥下体操」と「パタカラ体操」の2つの方法を紹介します。
嚥下体操
嚥下体操は、首や肩、胸郭、口腔器官の運動を行い、嚥下を行いやすくするための体操です。
深呼吸、首の回転・左右への傾け、肩の上下運動、背伸び、頬の運動、舌の運動、息の止め方、発声練習などを組み合わせて行います。
パタカラ体操
パタカラ体操は「パ・タ・カ・ラ」の発音を繰り返すことで、口や舌の筋肉を鍛える嚥下訓練の一つです。
具体的には「パ」「タ」「カ」「ラ」と順番に発音したり、1文字を4回ずつ発音したりします。
食事前に行うことで、誤嚥やむせを予防する効果があります。
継続することで、飲み込む力の維持・向上、口腔機能の改善が期待できます。
誤嚥が起こってしまったときの対処法
どんなに誤嚥が起きないように気をつけていても、高齢者の身体的な特徴から誤嚥は起こるものです。
誤嚥が起きても、慌てずに落ち着いて以下の対処ができるようにしておきましょう。
顔を下に向ける
もし誤嚥をしてしまったら、顔を下に向けて前傾姿勢を取ります。
のどよりも口のほうを下にさげることで、重力の働きによって異物が出やすくなります。
背中はたたくのではなく、優しくさするほうがよいでしょう。
背中を強くたたくことで、誤嚥した食べ物がさらに気管内に入り込んでしまうこともあります。
慌てるとつい背中を力いっぱいたたいてしまいがちですので気をつけましょう。
口腔内の異物を除去する
誤嚥が起こった際には、口の中に残っている異物をすぐに除去します。
口の中に異物がつまったままだと、さらに誤嚥や窒息を引き起こしてしまう可能性があり危険です。
自分で除去できそうであれば声掛けをし、口の中のものを吐き出すように誘導します。
また、自力で出すことが難しい場合には、顔を横向きにして、口の中に手を入れて異物をかき出します。
口の中に指を入れる際には、タオルやガーゼハンカチを指に巻いて保護しましょう。
咀嚼力が弱くなっている高齢者とはいえ、人の噛む力は予想以上に強いものです。
素手で口の中に指を入れると、介護する方の思わぬ大けがにつながります。
背中をさすったり軽くたたいたりする
のどに異物がつまっていないなら、背中を軽くたたいたり、さすったりすることで異物が出やすくなります。
力強くたたいてしまうと、異物を気管内に送り込んでしまいます。
背中をたたく際には、軽いタッチのタッピング程度の強さでたたくことがポイントです。
首筋から肩甲骨の間にかけてのタッピングやさすりは効果的です。
誤嚥をしてむせてしまうと本人も慌ててしまいます。
背中をさすってもらうことは安心感があるので、落ち着きを取り戻しやすくなります。
口呼吸を促す
口を閉じていると、異物はなかなか出てきません。
誤嚥をしてしまったら、口を開けた口呼吸をするように促しましょう。
口呼吸は体の力が抜けやすくなるため、異物を吐き出しやすくなります。
咳をする際にも口を開けたまま咳をするように促します。
口を開けたまま咳をすることで、より異物を吐き出しやすくなります。
ゆっくり息をするように声掛けをする
誤嚥をしたら、顔を下に向けたまま、ゆっくり呼吸をするように声をかけましょう。
激しくむせ込むと、呼吸ができなくなりパニックになってしまいます。
背中をさすりながら、ゆっくり呼吸をするように促し、落ち着くまで見守りましょう。
激しくせき込んでいる様子をみると、ご家族の方も慌ててしまいます。
慌てていると背中をさする速度も速くなりがちです。
背中をさする速度をスローテンポにすると、高齢者の方のパニックが落ち着き、声掛けも伝わりやすくなります。
ご家族の方も、一緒にゆっくり呼吸をして、スローテンポで背中をさすってあげましょう。
まとめ
高齢者は嚥下機能の低下によって、誤嚥しやすい状態となります。
食事の姿勢や食事の形態の工夫をすることで、誤嚥を予防することはできます。
誤嚥することで怖いのが誤嚥性肺炎の誘発です。
誤嚥性肺炎の予防のためにも、日頃の口腔ケアは念入りに行いましょう。
どんなに注意していても、誤嚥は起こり得るものです。
もし誤嚥してしまったら、落ち着いて対応しましょう。
いざというときに慌てないために、日頃から家族間で練習しておくのもおすすめです。