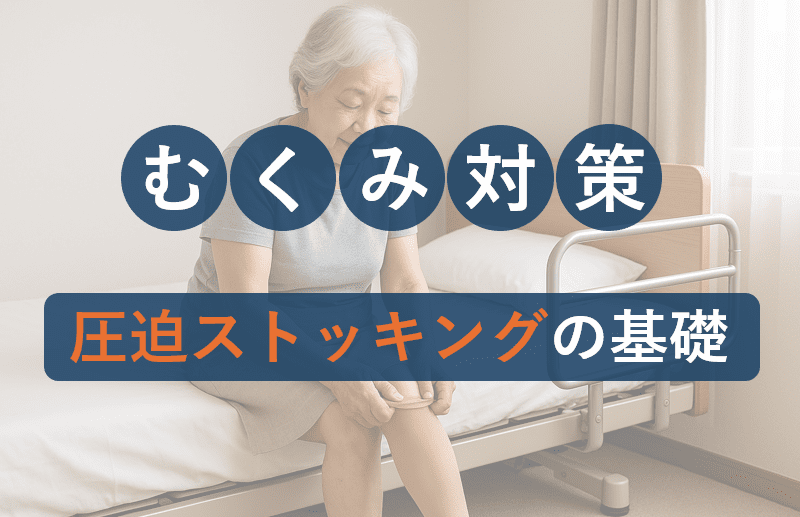更新日:
むくみ対策と圧迫ストッキングの基礎
足のむくみは、活動量や姿勢、塩分・水分の取り方など複数要因で変動します。圧迫ストッキングは正しく選び、適切な時間に装着してこそ力を発揮します。日常のケアと組み合わせて、張りやだるさの波を小さくするための基本を整理します。
注意点と装着タイミング
圧迫ストッキングは「正しいサイズ・適切な圧・無理のない時間」がそろって初めて快適に働きます。起床後のまだむくみが強くない時間に装着し、昼間の活動を支えるのが基本です。皮膚の弱さや循環の状態によっては使用を控える場合もあるため、違和感が続くときは専門職に相談し、無理に使い続けないことが安全です。
サイズ選びの目安
- 測るタイミング:むくみが軽い朝に、左右それぞれ測定します。
- 測定ポイント:足首(最も細い周径)/ふくらはぎ(最も太い周径)/膝下丈(床〜膝下)を基本に、膝下タイプを基準として選びます。太もも丈・パンティタイプは必要性が明確な場合に。
- 圧の強さ:初めての方や高齢者は弱〜中程度から。装着・脱衣に強い力を要する場合は、ドナー(装着補助具)や手袋の併用を検討します。
- 当て方の基本:かかと位置を合わせ、布を引っ張らず“たぐり上げる”。口ゴムは折り返さず、皺があれば整えます。
皮膚トラブルの観察
- 観察ポイント:着用30分・半日・脱衣直後に、赤み・色調変化(蒼白/紫)・冷感・しびれ・痒みを確認します。赤みが30分以上引かない、痛みやしびれが増す場合は一旦中止しましょう。
- 予防のコツ:爪は短く滑らかに整える/乾燥部位は薄く保湿/むくみの線が付きやすい口ゴム部は日に数回位置替え。濡れたまま履かず、汗をかいたら交換・洗濯を。
- 避けたい使い方:上端を折り返して二重にする、サイズが合わないのに無理に履く、就寝中に強圧で長時間固定する——いずれも血行障害や皮膚トラブルの原因になります。
- 装着タイミングの目安:起床後すぐ(または数分の足挙上後)に装着→日中の活動中は継続→夕方の入浴・清拭で一度外す→夜間は原則外す のが安心です。長距離移動や立ち仕事日は、昼休みに一度脱着して皮膚を確認しましょう。
生活の中でできる工夫
ストッキングだけに頼らず、「動かす・預ける・整える」を足すと効果が安定します。むくみやすい時間帯を把握し、ケアの順番を習慣化すると続けやすいでしょう。
足挙上と水分・塩分管理
- 足挙上:ふくらはぎ全体を10〜20cm持ち上げ、1回15〜30分を目安に朝夕など数回。膝裏や踵に一点圧がかからないよう、面で支えるクッションを使います。
- 足関節ポンプ:座位で足首の上下運動10〜20回、つま先上げ・かかと上げを交互に。少しでも歩ける方は、こまめな立ち上がりと室内歩行でふくらはぎを働かせましょう。
- 水分:喉が渇く前に少量を複数回。極端な制限は逆効果になり得ます。塩分は“濃い味を足さない”意識で、加工食品の頻度を調整します。
- 装着順序:朝は<軽い足首運動→短時間の挙上→装着>の順。夕方に強い張りが出る方は、帰宅後に挙上→軽運動→入浴→保湿→就寝まで非圧で休ませます。
就寝時の姿勢調整
- 面で支える:就寝中はストッキングを外し、ふくらはぎの広い面を支える低めのクッションで軽挙上。踵をわずかに浮かすと圧が分散します。
- つま先の自由:掛け布団が足先を押し下げると循環が滞りやすいため、布団アーチや軽いタオルケットでつま先スペースを確保します。
- 冷え対策:レッグウォーマーや薄手の保温靴下で冷えを避けつつ、口ゴムは跡が残りにくい柔らかいものを選びます。
まとめ
圧迫ストッキングは、朝に正しく装着・日中は活動を支援・夜は外して休ませるの三段構えが基本です。サイズと圧を見直し、皮膚サインをこまめに観察しながら、足挙上・軽運動・水分と塩分の整えを重ねると、翌日の足取りが軽くなるでしょう。違和感が続くときは無理をせず装着方法や製品を再評価し、ご自身の暮らしに合う“ちょうどよい続け方”を探してください。