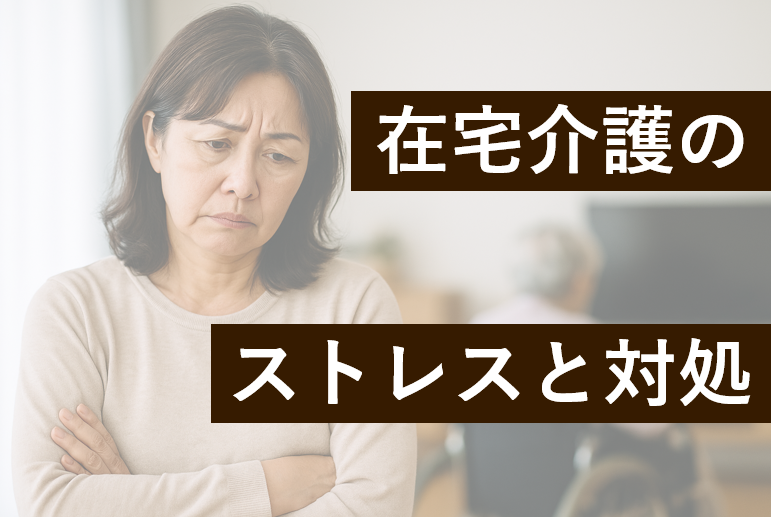更新日:
在宅介護のストレスと対処
在宅介護は、家族にとってやりがいのある一方で、長期化すると心身への負担が大きくなりやすいものです。ストレスの原因を整理し、適切な対処法や支援制度、介護用品を上手に活用することで、介護を続けやすい環境を整えられるでしょう。
ストレスの要因整理
在宅介護のストレスは、身体的・精神的・社会的な要素が重なって生じます。まずは自分の負担がどこから来ているのかを把握することが大切です。
睡眠・時間・身体負担
介護では夜間のトイレ介助や体位変換などで睡眠不足になりやすく、日中もケアに追われて休む時間が取れません。さらに、移乗や入浴介助など身体的負担の大きい作業が続くと、腰痛や関節痛など健康面にも影響します。
感情・孤立・情報不足
介護の長期化により、感情の起伏や孤立感が強まることがあります。介護方法や制度についての情報が不足していると、より不安や負担を感じやすくなるでしょう。
対処の基本
負担を減らすには、日々の生活に工夫を取り入れ、制度やサービスを積極的に利用することが重要です。
休息計画・レスパイト活用
計画的に休む時間を確保し、ショートステイやデイサービスなどのレスパイトケアを利用しましょう。介護保険制度を使えば費用負担を抑えてサービスを受けられます。
記録と家族共有
介護の記録を残すことで、体調変化やケア内容の把握が容易になります。家族やケアマネジャーと共有し、役割分担や改善点を話し合う機会を持つとよいでしょう。
介護負担軽減に役立つ用品
介護用品を導入することで、介護者と要介護者双方の負担を減らせます。
介護ベッド
介護ベッドは高さや背上げ・脚上げの調整ができ、移乗や体位変換の負担を減らします。移乗や体位変換は、時間がかかったりスムーズにできないと、双方にとって身体的負担が大きいので、介護ベッドの機能を活用しましょう。
歩行器・杖
歩行器や杖を使うことで移動時の転倒リスクを減らし、介助量を軽減します。自力で移動することで、要介護者の筋力維持にも効果があります。
まとめ
在宅介護のストレスは避けられない部分もありますが、制度・サービス・介護用品を上手に組み合わせることで負担を軽減できます。無理をせず休息を取り、家族や周囲と協力しながら、長く介護を続けられる環境を整えることが大切でしょう。