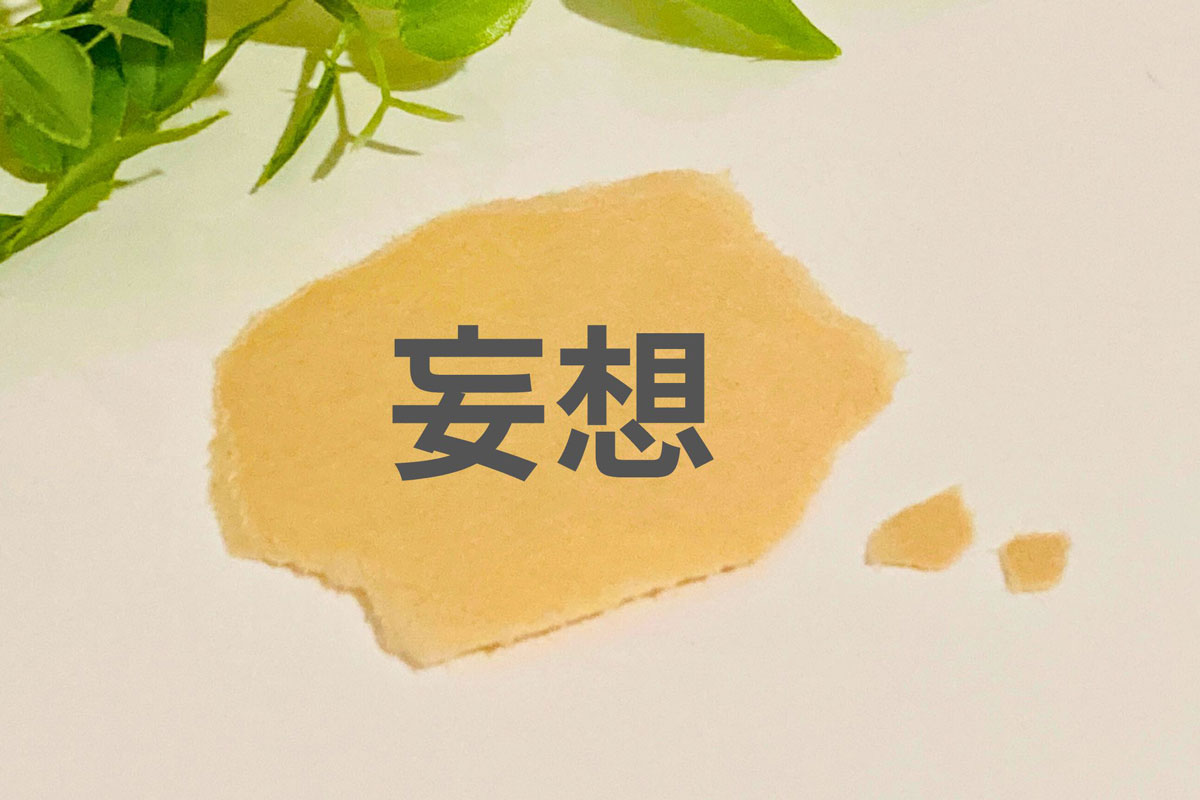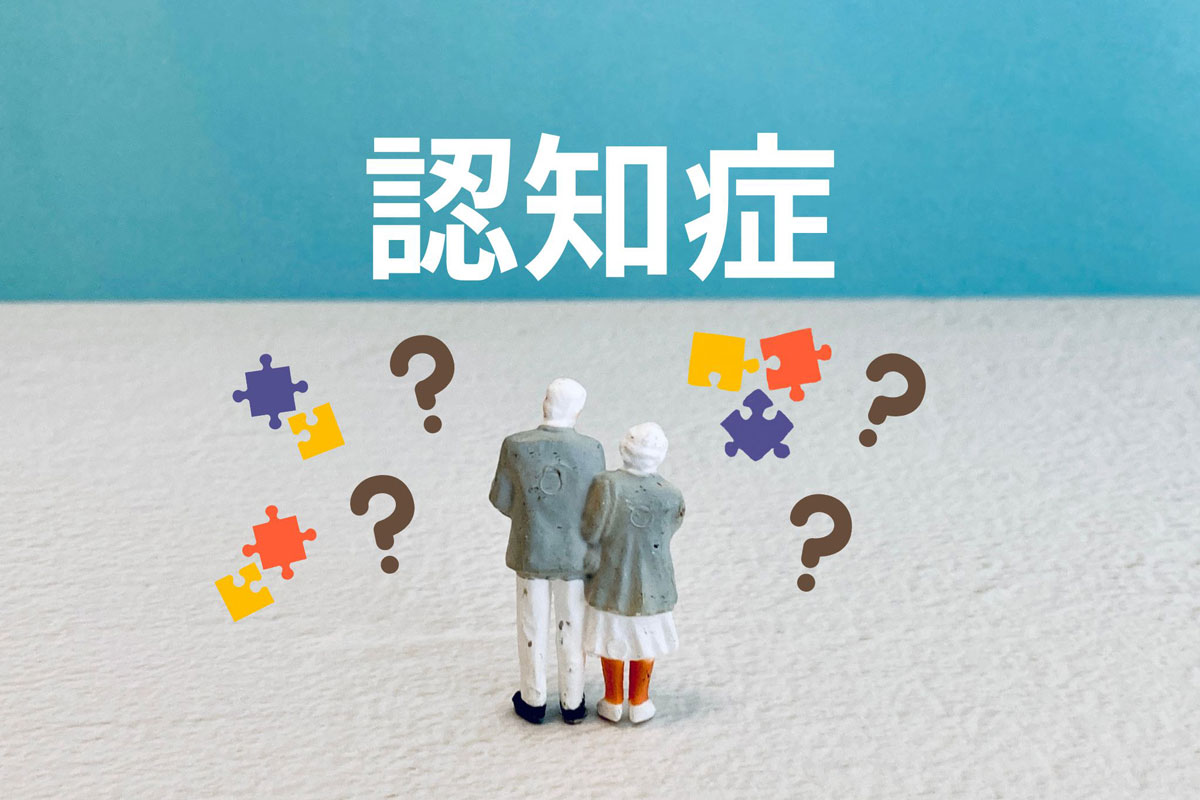更新日:
高齢者の妄想は認知症の初期症状?種類や対処法・治療方法を解説
高齢者の妄想は、認知症の初期症状としてあらわれることがあります。妄想は、事実でないことを本当であるかのように思い込んでしまうことです。周囲の人は妄想に振り回され、対応に苦慮することもあります。
今回は認知症高齢者の妄想について、種類や対処法、治療法などを解説します。
妄想は認知症の初期症状
認知症の初期症状には、以下の認知機能障害があります。
- 記憶障害
- 見当識障害
- 実行機能障害
- 理解・判断力の低下
- 幻覚症状
これらに加え、妄想も認知症の初期にあらわれやすい症状です。妄想が起こる原因は、上記の認知機能障害が背景になっていることが多いといわれています。
例えば、アルツハイマー型認知症では記憶障害や見当識障害がよくあらわれます。少し前の出来事や自分の置かれている状況がわからなくなり、不安や焦燥感に駆られ、徐々に妄想へと発展していくのです。
またレビー小体型認知症では、幻視や幻聴などの幻覚症状があらわれることがあります。実際には存在しないものでも、本人にとっては確実にあるように感じてしまいます。
そのため介護者からすれば、描写が細かく、リアルな妄想として捉えられてしまうのです。
認知症による妄想の種類
認知症によってあらわれる妄想には、以下の種類があります。
- 被害妄想
- 嫉妬妄想
- 物盗られ妄想
- 対人妄想
- 見捨てられ妄想
- 迫害妄想
- 幻覚・見間違い妄想
- 帰宅願望
それぞれの特徴を見ていきましょう。
被害妄想
被害妄想は、状況を理解する能力の低下から起こります。認知症になると、自分自身のことや周囲の状況を認識しにくくなるため、周りの人の行動が自分に対する攻撃であると思い込んでしまう場合があります。
- 息子夫婦が二人で話しているところを見て「私の悪口を言っている」
- 家族が自分をおいて外出すると「自分だけが仲間外れにされている」
- 嫁が私に暴力を振るってくる
- 近所の人が私のことを嫌っている
上記のような思い込みをしてしまうのです。
嫉妬妄想
配偶者やパートナーに対して、強い嫉妬心を抱いてしまうのが嫉妬妄想です。
内容は非現実的であるものの、描写が細かく、リアルな妄想となってあらわれます。たとえば「配偶者が浮気し、不貞行為をしている」といった内容です。
一度思い込んでしまうとなかなか修正できず、相手を強く非難する傾向があります。嫉妬妄想の矛先は、時に浮気相手だと思い込んでいる人に対しても向く場合があります。
例えば郵便配達に来た人を疑っている場合、配偶者が荷物を受け取ってほんの少し世間話をするだけでも「あいつが私の配偶者と浮気していた」と強く思い込んでしまうのです。
物盗られ妄想
妄想の中でもよく見られるのが、物盗られ妄想です。
「財布や服を盗まれた」などと言って騒ぎ立てます。自宅では嫁やヘルパーなどに疑いの目をもち、施設入所者中では隣の部屋の利用者や職員などが対象になることもあります。
物盗られ妄想の原因は記憶障害です。本人が、物忘れをしてしまう現実を認めたくないために起こる反応と考えられています。
自分の弱みが明るみに出ないように、誰かに盗られたと思い込むことで、徐々に妄想へと発展していくのです。
対人妄想
対人関係に関わる妄想です。嫉妬妄想のように、リアルで細かい妄想となってあらわれます。
- 誰かが家に入って、タンスの中を物色して出ていった
- 食卓に置いてあったおやつを隣の家の人が勝手に食べた
上記のような内容です。
描写があまりにもリアルであるため、本人の状態を詳しく知らない人が訴えを耳にすると、鵜呑みにしてしまうことがあります。そして心配になって警察に相談し、騒動になることもあります。
見捨てられ妄想
物盗られ妄想の次に多く見られ、自分を客観視できる人にあらわれやすいタイプの妄想です。
認知症になってできないことが増えてくると、周りに迷惑をかけていると思い込み、介護者への負い目を感じるようになります。
負い目が強くなると「自分は誰からも必要とされていない」と思うようになり、孤独感に襲われてしまいます。
すると他者との交流や外出を避けるようになり、徐々に心身機能が低下してしまう負の連鎖へと陥ってしまうのです。
迫害妄想
いじめを受けていると思い込むタイプの妄想です。
- 家族や近所の人にいじめられている
- 知らない人からつけられている
上記のような思い込みが特徴です。
ささいなできごとや他人の言動を、自分への攻撃ととらえてしまいます。本人は色々なことに疑心暗鬼になってしまい、監視カメラや盗聴器などを探して家中歩き回ったり、家族に探させたりすることもあります。
周りの人は本人の言動に振り回されてしまい、心身が休まりません。
幻覚・見間違い妄想
レビー小体型認知症に多く見られるタイプの妄想です。幻覚がきっかけになり、さまざまな妄想へと発展します。
幻覚とは以下の症状です。
- 幻視:見えないものが見える
- 幻聴:実際に聞こえない音や声が聞こえる
幻覚をきっかけとした妄想は細かくリアルであり、以下のように訴えたり行動したりします。
- 部屋のすみに子供がいて手招きをしている
- 死んだ親が近くで呼んでいる
- 落ちているゴミが虫に見えて追い払おうとする
見間違い妄想は、実際に見たものを別のものと誤認してしまうことです。
ハンガーにかかっている服が人影に見えたり、木の陰を恐ろしい生き物と勘違いしてしまったりします。
帰宅願望
帰宅願望は、見当識障害がきっかけになり起こる症状です。「家に帰りたい」と訴えて、出口を探して徘徊してしまいます。
今いる場所がどこだかわからないため、安心できる我が家に帰りたくなってしまうのです。
- 子供たちにご飯を食べさせないといけない
- 明日は仕事が早いからすぐに帰らないといけない
このような訴えを起こすことがあります。帰宅願望は多くの場合、自分がもっとも元気であったり一生懸命働いていたりした頃の自分であると思い込んでいます。
妄想の対処法
ここでは妄想の対処法について解説します。妄想には、以下のように対処しましょう。
- 妄想の内容を否定せず共感する
- 自分だけで対処しようとしない
- 時には距離をとる
妄想は、否定するとより強くなることがあります。そのため、否定せず本人の訴えに共感することが大切です。
認知症の症状によって、本人は不安や焦燥感といった負の感情を抱いています。本人が抱えている感情を読み取り「つらかったでしょう」と声をかけ、話を聞く姿勢を見せましょう。
しかし、常に同じ介護者が対応するのにも限界があります。一人の介護者に負担がかかりすぎないように、他の家族やヘルパーなどの手も借りながら、複数人で関わりましょう。
時には距離をとって、介護者が心を休ませられる環境をつくることも大切です。
妄想の治療方法
妄想の治療には、薬物療法が選択されます。治療に使われる薬には以下があります。
- 抗認知症薬:メマリー
- 抗精神病薬:リスペリドン、オランザピン、アリピプラゾール、クエチアピンなど
- 漢方薬:抑肝散
これらの薬は、急にたくさん飲んではいけません。副作用の有無を見ながら、注意深く種類や量を決める必要があります。
詳細は医師が指示するため、自己判断で調整しないようにしましょう。
認知症の方は副作用によって体調に異変が起きていても、自分で訴えられない場合があります。周囲の人が変化に気づき、何かあればすぐに受診する体制を作っておくことも大切です。
【参考】
かかりつけ医のためのBPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第2版)
抑肝散の認知症症状に対する薬理学的検証
まとめ
高齢者の妄想は、認知症の初期症状のひとつとしてあらわれます。認知機能障害によって不安や焦燥感に駆られ、本人もつらく寂しい思いをしています。
治療には服薬が選択されますが、周囲からの理解と適切な関わりを心がけることも大切です。
「なぜそのような思い込みをするのか」を考え、本人の気持ちに寄り添った対応を心がけましょう。